医療コラム

胃カメラ検査は、内視鏡スコープで食道、胃、十二指腸の粘膜を直接観察する検査で、胃がんをはじめとした多くの病気の早期発見と治療に役立ちます。胃カメラのスコープは細くなり、苦痛を和らげる検査方法も広くおこなわれるようになり、検査自体のハードルは以前に比べて低くなっています。
一方、胃カメラ検査は、症状があり医師から指示されて受ける場合や、健康診断や人間ドックで受ける機会がありますが、費用はどれぐらいかかるのか、不安に思う方も少なくないでしょう。胃カメラ検査の費用相場や費用を抑える方法を知ることで、不安を少しでも払拭できれば、安心して検査に臨むことができるはずです。ここでは、胃カメラ検査の費用相場を中心に気になる胃カメラ検査の費用が変わる点や費用負担を抑える方法まで詳しく解説します。
胃カメラ検査を受けることになった時、やはり心配なのは費用の面ではないでしょうか。ここでは、胃カメラ検査の費用の目安と費用の内訳について説明します。費用については、令和6年度の診療報酬点数に基づき算出しています。
胃カメラ検査の費用の目安は、胃カメラ検査が保険診療でできる場合と、自由診療で受ける場合で大きく異なります。基本的に、何らかの症状があり、医師が診断のために胃カメラ検査が必要であるとした場合には保険が適用されます。国民皆保険の日本では、年齢により1~3割の自己負担で検査を受けることができます。
一方、症状がなく、健康診断や人間ドックとして胃カメラ検査を受ける場合には、保険の適用にはならないため自由診療となり全額自己負担です。
また、胃カメラ検査が観察だけの場合と、検査中に疑わしい点があり組織を採取して病理組織検査がおこなわれる場合で、胃カメラ検査の総費用は変動します。
これらを踏まえて、保険診療と自由診療における胃カメラ検査の費用の目安を紹介します。
保険診療の場合は、胃カメラ検査の費用が診療報酬制度によって定められているため、検査費用自体は3,420円(3割負担)で、どの医療機関でも同じです。これに検査に必要な薬剤や検査が上乗せになり、さらに病理組織検査が必要な場合にはさらに加算されます。保険診療であっても、医療機関によって加算される費用は多少の違いがあります。
・胃カメラ検査(観察のみ)
胃カメラを用いて食道、胃から十二指腸の一部までを観察し、異常がないか確認する検査です。以下には、検査に必要な薬剤などの費用が含まれています。
・胃カメラ検査+病理組織検査
胃カメラを用いて疑わしい箇所を発見した場合に、組織を採取(内視鏡下生検)して顕微鏡で観察し病理診断する検査です。以下には、検査に必要な薬剤などの費用が含まれています。
自由費診療の場合は、医療機関が自由に費用を決めることができるため、その費用には幅があり高額を設定していることもあります。当院においては、自由診療における胃カメラの費用は20,000円となっております。生検などを行った場合、追加費用が必要になります。
1.2.胃カメラ検査の費用内訳
胃カメラ検査の費用の中には、検査費用のほかに、検査中に使用する薬剤のほか、処置や検査にともなうさまざまな費用が発生し加算されます。医療機関で会計の際に発行される診療明細書には、かかった費用の内訳が記載されていますので、確認するようにしましょう。ここでは、胃カメラ検査費用の内訳について説明します。
▼診察料
医療機関を受診した時に、必ずかかる費用です。初めての受診では初診料として890円(3割負担)、2回目以降は再診料として390円(3割負担)がかかります。ただし、医療機関の規模や設備などで、別途追加費用が加算される場合もあります。
・胃カメラ検査
基本的な胃カメラ検査の費用は3,420円(3割負担)です。この金額に、染色を施し病変部を浮かび上がらせて観察する場合(色素内視鏡法加算)には180円(3割負担)が加算されます。
・薬剤費
胃カメラ検査の際には、のどや鼻の麻酔薬、胃の泡を消す薬、胃の粘膜を溶かす薬などを使用します。使用する薬剤や剤型(スプレー、ゼリーなど)によって違いがありますが、合計200円(3割負担)程度です。
また、胃カメラ検査では、検査時の苦痛を和らげるために、鎮静剤を使用することがあります。使用する薬剤ごとに違いがありますが約100~300円(3割負担)程度です。
・病理組織検査費
検査中に疑わしい病変部がみつかった場合に、内視鏡ファイバーを用いて組織を採取し、顕微鏡で観察し病理診断をおこなうことがあります。病理組織検査費として、内視鏡下生検法310円~620円、病理組織顕微鏡検査1,720円、病理診断料390円がかかり、合計で2,420円~2,730円がかかります。
・ピロリ菌検査
胃カメラ検査で胃潰瘍・十二指腸潰瘍が確認されたり、胃炎の症状が確認できたりした場合など、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われた場合にピロリ菌検査をおこなうことがあります。ピロリ菌検査の方法によって違いがありますが、1,500円程度(3割負担)の費用がかかります。

胃カメラ検査の費用は、検査前に分かっている費用(胃カメラ検査の費用、使用薬剤など)のほかに、検査中の状況によって追加になる費用(病理組織検査、ピロリ菌検査など)があり、最終的な費用は変動します。胃カメラ検査の費用が変わる3つのポイントと費用の差について説明します。
胃カメラ検査には、内視鏡ファイバーを口から挿入する方法(経口胃カメラ)と、鼻から挿入する方法(経鼻胃カメラ)があります。基本的な胃カメラ検査の費用はいずれも3,420円(3割負担)です。当院において、基本的な観察や生検をする胃カメラであれば、経口と経鼻で費用は変わりません。経口と経鼻では、それぞれメリット・デメリットがあり、検査の前に費用面での違いも聞いておくと良いでしょう。
経口胃カメラ検査の場合、口から内視鏡スコープを挿入する苦痛やのどの反射を和らげるため、静脈注射で鎮静剤を使用し、うとうとした状態で検査をする医療機関が増えています。経口胃カメラ検査で鎮静剤を使用する場合には、鎮静剤の費用がかかるため、経鼻胃カメラ検査より20~160円(3割負担)程度高くなります。
検査費用が変わる大きなポイントとして、胃カメラ検査中に追加の検査が必要になった場合があります。例えば、疑わしい病変が見つかった場合におこなう病理組織検査では、基本的な胃カメラ検査の費用のほかに合計で2,420円~2,730円(3割負担)が、ピロリ感染が疑われた場合おこなわれるヘリコバクター・ピロリ検査では、検査方法により約1,500円(3割負担)の費用が加算されます。
胃カメラ検査の費用は保険適用されるか否かで大きく異なります。どのような時に保険が適用されるのか抑えておきたいものです。保険適用になる場合と自由診療になる場合の条件について説明します。
胃カメラ検査が保険適用になるのは、医師が「胃カメラ検査の必要性がある」と判断した場合です。例えば、以下のようなケースでは、その原因を明らかにし診断・処置する目的で胃カメラをおこなうため、保険適用になります。
医師の判断ではなく、自分の判断で胃カメラ検査を受ける場合は、基本的に自由診療となり、胃カメラ検査の費用は全額自己負担となります。以下に自由診療となるケースを紹介します。

胃カメラ検査は自由診療の場合はもちろん、保険適用になったとしても高額な検査といえます。少しでも費用負担を抑える方法として、企業や行政の助成金制度や、国の医療費控除制度があります。以下にその制度と利用方法を説明します。
社会保険に加入している場合、所属の健康保険組合から胃カメラ検査の費用の一部が補助されたり、健康診断にオプションとして胃カメラ検査を追加した場合、その差額が補助されたりする制度が利用できることがあります。また、本人だけでなく扶養家族も対象になる場合もあります。助成制度の対象や検査内容などを、健康保険組合に確認して利用すると、負担額を抑えることができます。
何も症状がないため自由診療になるケースでは、自治体の胃がん健診を利用すると、費用を抑えることができます。自治体の胃がん健診ではバリウム検査の場合がありますが、助成金があり、少しの費用で胃カメラ検査を受けられる自治体が増えています。任意で申し込みをする場合や、個別に自治体から受診券が送られてくる場合などがあります。
また、国民健康保険の場合、人間ドックに対する助成制度があります。助成制度の有無や金額、具体的な条件などは自治体によって異なるので、お住まいの自治体に問い合わせてみましょう。
胃カメラ検査を保険診療で受けた場合、医療費控除制度を利用すると、1年間に支払った医療費の全額が10万円を超えた分について、所得税や住民税が軽減されたり、一端支払った税金が還付されたりする場合があります。医療費控除制度を利用するには、翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。扶養家族の医療費や医療費控除の対象になる市販の医薬品、交通費なども医療費控除の対象になるため、医療費の明細書や領収書はしっかり保管するようにしましょう。
胃カメラ検査というと、苦しい上に費用が高いなど、悪いイメージを持っている方も少なくありません。最近の胃カメラ検査は、内視鏡ファイバーが細く、鎮静剤を使うことで苦痛も少なくなっています。また、費用に関しては、一般的に症状があれば保険適用になり、社会保険や自治体からの助成金や補助が利用できる場合もあるため、自己負担額を抑えることもできます。胃カメラ検査は、その画像も鮮明で診断能力が高く、多くの胃の病気の診断と治療に役立つ検査です。医師の指示がある場合には、検査や費用に対する不安を解消して、積極的に胃カメラ検査に臨むことをおすすめします。

食道がんや胃がんなどの早期発見に欠かせない胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)。胃カメラ検査には、内視鏡を口から挿入する方法と、鼻腔より挿入する方法の2つのアプローチがあります。
ここでは、胃カメラを口からあるいは鼻からおこなう場合のそれぞれの特徴を、メリットやデメリットを比較しながら詳しく解説します。これから胃カメラを受けようという方が気になる「検査の痛みや苦痛」や、鎮静剤を使った“苦しくない胃カメラ検査”についてもご紹介します。
口からおこなう胃カメラ検査は、経口内視鏡検査とも呼ばれ、名前の通り口から内視鏡を入れて胃の内部を観察する方法です。胃カメラの中で最もよくおこなわれる方法で、喉に局所麻酔をしてから、口にマウスピースをはめた状態で横になり、先端部径5.8mm程度の内視鏡を飲みこんで検査します。多くの病院では経口内視鏡は10mm程度の太径のものを用いますが、当院では苦痛に配慮するため、経口の場合でも5.8mmのものを使用しており、嘔吐反射が格段に抑えられています。検査の所要時間は7~8分程度です。
経口内視鏡検査のメリットは、経鼻内視鏡検査のデメリットを回避できる点です。経鼻内視鏡検査の場合は、鼻腔を広げるためにスプレーをし、効果が出るまで約10分待つ必要がありますが、経口内視鏡検査ではそのような待ち時間は発生しません。
また、経鼻内視鏡検査のように鼻に痛みが出たり、鼻血が出たりすることもありません。
経口内視鏡検査のデメリットは、嘔吐反射が起きやすいことです。嘔吐反射とは、喉に異物が触れた際に「オエッ」となる生理反応のことです。口から飲み込むことに心理的な抵抗感を感じてしまう方もいます。
その他、検査中は医師と会話ができないこともデメリットの一つです。また、検査中は口を大きく開けたまま維持しなければならないので、顎関節症の方や、歯の矯正器具や入れ歯を使用中の方は、検査を受けにくいこともあります。
鼻からおこなう胃カメラ検査は、経鼻内視鏡検査といいます。先端部径5.8mm程度の細い内視鏡を鼻から挿入し、喉の奥を通して胃の中に挿入する方法です。はじめに鼻腔を広げるスプレーをして10分待ち、鼻の局所麻酔をして、鎮静剤をご希望であれば鎮静剤を投与して検査を開始します。検査の所要時間は経口内視鏡検査と同様に7~8分程度です。
経鼻内視鏡検査の最も大きなメリットは、経口内視鏡検査に比べて嘔吐反射や痛みが生じにくく、比較的楽に検査を受けられることです。カメラ挿入時の身体への負担が少なく、検査中も医師と会話ができるのもメリットです。また、入れ歯を外す必要がないため、歯科治療をしている方も安心して検査を受けることができます。
その他、鼻から食道に至る間に、咽頭や喉頭などに異常がないか調べやすい点もメリットの一つです。
デメリットとしては、「鼻腔が狭くて通らない人がいる」ことです。生まれつき鼻腔が狭い方や、鼻中隔湾曲症(びちゅうかくわんきょくしょう)といって、左右の鼻腔を隔てる真ん中の仕切りの骨が曲がっている方は、挿入時に強い痛みをともなうことや、検査自体が実施できないことがあります。このような場合には、経口内視鏡検査に切り替えて実施することになります。

胃カメラ検査には、先ほど解説した口からと鼻からの2つのアプローチの方法があり、それぞれに鎮静剤を使用するパターンと使用しないパターンの計4通りの方法があります。それぞれ詳しくみていきましょう。
鎮静剤を併用し、口から内視鏡を入れる方法です。鎮静剤とは、いわゆる「麻酔薬」のことで、点滴ルートから鎮静剤を導入し、鎮静剤が効いてからカメラを挿入します。ほぼ眠ったまま検査を受けることができるので、径の太いカメラでも、通常痛みや苦しさを感じることはなく、「気づいたら検査が終わっていた」ということが多いです。
鎮静剤を併用する方法は、胃カメラ検査への不安感が強い方や、嘔吐反射の強い方、過去に胃カメラで苦しい経験をした方に適しています。
しかし、デメリットとして検査後に覚醒するまで30分~1時間程度の休息が必要であり、すぐに帰宅することができないことや、検査当日は自転車やバイク、車の運転を控えるなどの行動制限があること、鎮静剤の副作用で血圧低下や呼吸抑制などが起きるリスクがあることなどが挙げられます。また、心臓病などの持病がある方には、鎮静剤の併用ができないこともあるので、医師に事前に相談する必要があります。
意識がはっきりした状態で、口から内視鏡を入れる方法です。はじめに、嘔吐反射が起きにくくするために、のどの奥に局所麻酔薬を5分ほど溜めて、のどの感覚を鈍らせます。喉の局所麻酔が効いたら、横になってマウスピースをはめ、口からカメラを挿入します。
鎮静剤なしで口からカメラを入れる方法は、嘔吐反射が弱い方や、胃カメラへの不安感が少ない方、仕事の都合などでどうしても検査当日の乗り物の運転をしなくてはならない方、検査後すぐに帰宅したい方、鼻からカメラが通りにくい方などに向いている方法です。
ただし、デメリットとして、鎮静剤を併用しないので、喉に局所麻酔が効いている状態であっても口からカメラを入れるときに痛みや嘔吐反射が生じやすく、検査中も胃の中に不快感を覚えやすいという点が挙げられます。また検査中に不安になり、極度に緊張してしまうなど、精神的にも負担が大きいという点も考慮する必要があります。
鎮静剤を併用し、鼻から内視鏡を入れる方法です。鎮静剤で眠った状態で細いカメラを鼻から挿入するので、ほとんど苦痛を感じることなく検査を受けることができます体質的に鎮静剤が効きにくい方で嘔吐反射が強い方については、経鼻+鎮静ありの検査が検討されます。
意識がはっきりした状態で、鼻から内視鏡を入れる方法です。「経鼻+鎮静剤なし」は、嘔吐反射が強いために「経口+鎮静剤なし」が不向きな方に向いている方法です。鎮静剤を使用しないので、検査後の行動制限もなく、乗り物の運転もできるので、検査後すぐに出勤したい方や帰宅したいという方はこちらを選択することになります。そのほか、心臓病などの持病があって鎮静剤を使用できない場合でも、経鼻内視鏡であれば、鎮静剤なしでも比較的苦痛が少なく、胃カメラ検査を受けることができます。
ただし、デメリットとしては、鎮静剤を使用しないため、鼻粘膜に局所麻酔が効いていても、鼻からカメラを挿入するときに不快感や痛み、息苦しさを感じる場合があることが挙げられます。また、もともと鼻腔が狭い方は、カメラが入りにくく、挿入時の痛みが強かったり、摩擦によって鼻粘膜から軽い出血が起きたりするリスクもあります。鼻からカメラが入りにくい場合は、検査を中断し、口からのアプローチに変更することになります。
つらいと思われがちな胃カメラ検査ですが、検査の痛みや苦しさや痛みを軽減し、楽に受けるためのポイントがあります。
まず1つ目のポイントは、鎮静剤を併用することです。鎮静剤を使用することで、ウトウトと眠ったまま、痛みや苦しさ、不安を感じることなく検査をうけることができます。どうしても胃カメラ検査に抵抗感がある方や、不安になりやすい方、過去に受けた胃カメラでつらい経験をした方などは、鎮静剤の併用を検討しましょう。
一方、鎮静剤を使用せずに、胃カメラ検査を受ける場合でも、以下の6つのポイントを意識することで、検査の苦痛を軽減することができます。
胃カメラ検査の痛みや苦しさを軽減する6つのポイント
まず、検査室に入ったら心身共にリラックスするように心がけましょう。緊張して肩に力が入ったり、肩で息をしてしまったりすると、呼吸が乱れて苦しくなってしまいます。肩の力を抜いて、ゆっくり大きな深呼吸をして気持ちを落ち着けましょう。
いよいよ、カメラを入れるというタイミングでは、のどの力を抜くように意識し、担当医の指示に従って呼吸と飲み込む動作をしましょう。検査中、のどに力を入れて構えてしまうと、嘔吐反射が起きやすくなったり、カメラが通る時に痛みが生じたりする原因になりますので、リラックスを心がけることが大切です。
なお、検査中は目を閉じたくなりますが、目を開けて遠くをみるようなイメージを持つのもポイントです。目を閉じてしまうと、のどの違和感に意識が集中してしまい、嘔吐反射が出やすくなるからです。
検査の後半は、カメラから胃の中に空気を送り込んで、胃を膨らませた状態で観察します。ゲップが出そうになりますが、ゲップをしてしまうと再び膨らませる必要があり、その分検査時間が長くなってしまいます。医師から「終わりましたよ」「もういいですよ」といわれるまではゲップを我慢しましょう。
つらくない胃カメラ検査を受けるためには、病院選びが大切です。内視鏡専門医が検査を実施するのか、鎮静剤の使用の選択肢があるかどうか、経口内視鏡あるいは経鼻内視鏡の選択肢があるかどうかなどを比較しましょう。
胃カメラ検査に熟達した消化器内科専門医のいる病院では、内視鏡も最新機器を導入しており、医師をはじめとして看護師などのスタッフも経験が豊富なため、スムーズかつ患者さんに寄り添ったきめ細やかなサポートを受けることができます。
胃カメラ検査の際の痛みや苦しさは、何よりも担当医の技量によって大きな差が出るため、経験豊富な内視鏡専門医が検査をおこなっている病院を選びましょう。
西宮敬愛会病院 低侵襲治療部門COKUでは消化器内視鏡専門医・指導医資格を持つ経験豊富な内視鏡医が胃カメラ検査を担当します。鎮静剤の使用が可能で、高い内視鏡挿入技術に加えて、最新の内視鏡システムを使用することで苦しくない検査を提供しています。当院が主に使用する最新の内視鏡は、先端部が径5.8mmと極めて細い高画質細径カメラであり、患者さんの状態に応じて鼻からでも口からでも挿入可能です。さらにAIによる見落とし防止システムを導入し、疑わしい場所をAIが検出ボックスで囲んで表示することで、診断精度を高めています。
患者さん一人一人の状態にあった検査方法をご提案していますので、ぜひご相談ください。
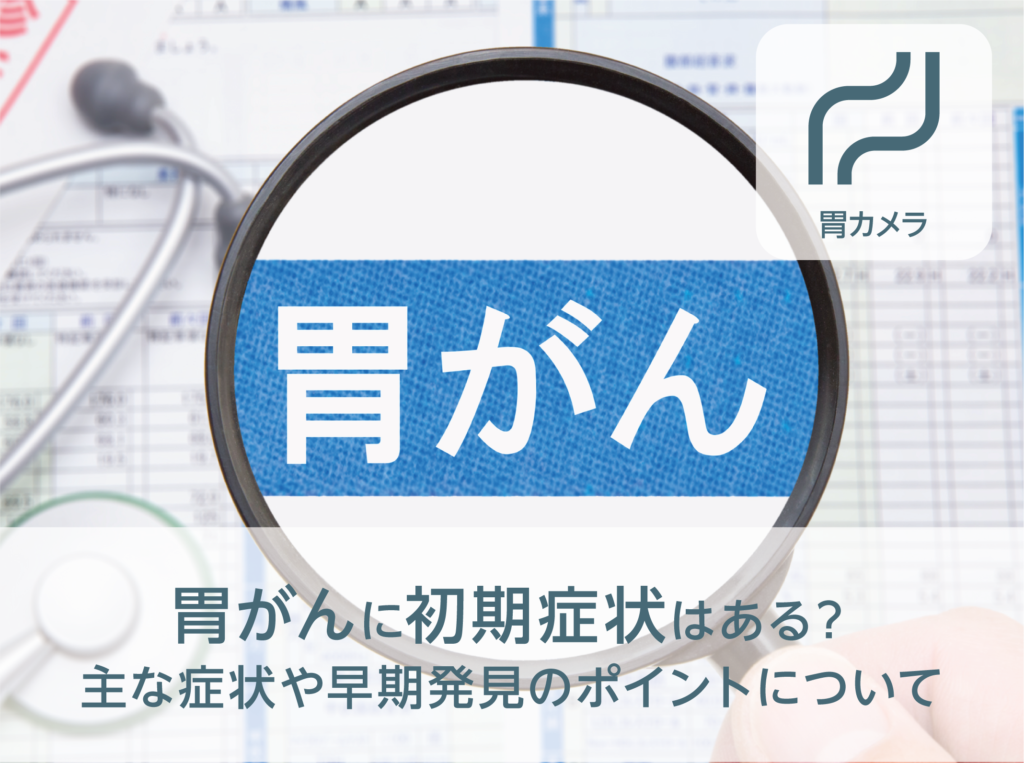
かつて胃がんは、日本人のがんによる死亡数の第1位でしたが、近年では診断技術が発達し、早期治療をおこなうことで完治も目指せるようになっています。しかし胃がんは初期症状がほとんどないため、本人が気づかないうちに発症し、進行してしまうことが多く、早期発見のためには胃がん検診が欠かせません。今回は、胃がんの症状について詳しく解説するとともに、国が推奨する胃がん検診の概要やメリット・デメリットについてもお伝えします。胃がんに対する正しい知識を踏まえて、胃がんの早期発見・早期治療につなげましょう。
胃は消化器系の一部であり、みぞおちのあたりにあります。袋状の構造をしていて、上部は食道、下部は十二指腸につながっています。食道とつながる入口の部位を「噴門(ふんもん)」、十二指腸につながる出口の部位を「幽門(ゆうもん)」といいます。
胃は消化器系の臓器のなかでも最もよく拡張し、食べ物をたくさん食べると最大容量は1,200~1,500mLほどになります。
胃の壁は、内側から「粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜」と呼ばれる4層から成り立っています。健康な胃の粘膜は、均一でみずみずしいピンク色をしているのが特徴です。
胃の主な役割は、食べ物の貯蔵と消化です。胃に食べ物が入ってくると、一旦胃の中に貯蔵し、蠕動運動(ぜんどううんどう)をしながら胃液と混ぜ合わせることで、食べ物を吸収しやすい形へと変化させ、幽門から十二指腸へと少しずつ送り出します。
胃がんは、胃の壁を覆う粘膜の表面から発生するがんです。がん細胞が、粘膜や粘膜下層などの表層部分にとどまっているものを早期胃がん、それよりもさらに深い固有筋膜以上に達しているものを進行胃がんといいます。胃がんになっても、初期症状はほとんどなく、自覚するのは困難です。ある程度がんが進行していても、無症状のケースもあります。
がんが進行し、自覚症状がある場合には、胃の痛みや不快感、違和感や胸やけ、食欲不振、嘔気でなどの症状が出たり、あるいはがんからの出血によって貧血や黒っぽい便(タール便)が出たりするケースもあります。しかしこれらの症状は、胃炎や胃潰瘍などの病気でも起こることがあり、胃がんに特有の症状というわけではありません。そのため、胃がんを特定するためには胃がん検診を受ける必要があります。

胃がんの診断は、「胃内視鏡検査(胃カメラ)」による胃の中の観察と、実際に組織を採取して顕微鏡で観察する「病理組織検査」でおこないます。それぞれ詳しくみていきましょう。
胃内視鏡検査(胃カメラ)は、胃の内側をカメラで直接観察して調べる検査です。口あるいは鼻から、細い内視鏡を胃まで挿入し、胃粘膜の色調や形状に異常がないか詳細に調べます。高画質のカラー画像で観察しますので、ほんのわずかな色調変化や組織の異常を検出することができ、ごく初期の胃がんの発見にも威力を発揮します。がんが疑われる部位が見つかった場合は、検査中に組織を採取(生検:せいけん)して、精密検査に出すことができます。胃がんは自覚症状がほとんどないため、胃カメラは、胃がんの診断において欠かすことできない重要な検査です。
その他、医師の判断で胸部・腹部CT検査やバリウム検査、超音波検査などの画像検査を併用することもあります。
生検で採取した組織を、顕微鏡を使って詳細に観察して、がん細胞があるか検査します。これを病理組織検査といいます。病理組織検査をおこなうことで、胃潰瘍や胃炎などのそのほかの病気との鑑別、がん細胞の有無がわかります。また、胃がんと診断された場合、この病理組織検査によってがんの種類や進行度などを調べることができます。
胃がんは早期に発見すれば、ほぼ完治が可能な病気です。胃がんを早期に発見し、治療につなげるための方法と注意点について解説します。
胃がんは、特有の初期症状がほとんどないため、知らないうちに発症して進行してしまうことがあります。胃がんを早期に発見するためには、定期的に胃がん検診を受けることがとても大切です。
胃がんは、40歳代から増えはじめ、50歳以上になると罹患率が本格的に増えはじめることから、厚生労働省は、50歳以上の人に対し、2年に1回定期的に胃がん検診を受けることを推奨しています。国が推奨する胃がんの定期検診は、問診および胃部X線検査、もしくは問診および胃内視鏡検査(胃カメラ)のいずれかです。自覚症状がなくても、検査対象年齢に達したら、定期的に胃がん検診を受けましょう。
がん検診には、利益と不利益があります。がん検診の利益とは、胃がんで死亡することを防ぐことを指します。対して不利益とは、偽陰性、偽陽性などを指します。胃がん検診を受ける際には、利益が不利益を上回るという科学的根拠が確立されたがん検診を選ぶことが大切です。国が推奨する胃がんの対象年齢や検査項目、受診間隔は、この科学的根拠に基づいて判断したものです。したがって、胃がん検診は、やみくもに受けるのではなく、推奨される年齢と間隔で受診することが大切です。

胃がん検診を受けるメリットは主に2つあります。1つ目は、胃がんを早期に発見し、早期治療を受けることで根治できる可能性が高くなるので、胃がんによる死亡を防ぐことができることです。
2つ目のメリットは、がんが初期のうちに早期治療をおこなうことで、治療による負担を軽減できることです。そのほか、異常がないかどうかの確認ができることで、胃がんに関する不安を払拭できることもメリットといえます。
胃がん検診の主なデメリットは3つあります。1つ目は偽陰性または偽陽性の可能性があることです。偽陰性とは、実際にはがんがあるのに、精密検査が不要と判断されてしまうことをいいます。偽陰性によってがんの発見・治療開始が遅れることがあります。また、偽陽性とは、実際にはがんがないのに、がんの疑いがありと判断されることをいいます。偽陽性によって、不必要な精密検査を受けることになり、検査にともなう負担がかかります。
2つ目のデメリットは、過剰診断です。成長のスピードが極めて遅いタイプのがんなど、すぐに治療しなくても命に関わることのないがんに対して、治療を進めることになるため、患者さんに負担がかかります。
3つ目のデメリットは、偶発症です。ごく稀に、内視鏡による手技やバリウムの誤嚥(ごえん)、排出不全などによって、出血や穿孔(せんこう:消化管に穴が開くこと)、腸閉塞など予期せぬ合併症を発症するリスクが存在します。
このように、胃がん検診には少なからずデメリットも存在するため、推奨年齢よりも若い方が検診を受けた場合、メリットよりもデメリットが上回ることがあります。
国が定期的な胃がん検診の受診を推奨している50歳以上の方については、定期的に検診を受けることが非常に重要です。ただし、推奨年齢以下の方であっても、胃や胸の痛み、胸やけや吐気、便の色がおかしいなど、心配な症状がある時は胃がん検診を受けることをおすすめします。早めに消化器内科を受診して医師に相談しましょう。
胃がんは初期の段階で発見し、早い時期に治療を開始することができれば完治を目指せる病気です。しかし胃がんは初期症状がほとんどないため、50歳になったら定期的に胃がん検診を受けて、早期発見・治療につなげることが大切です。胃がん検診は、推奨された年齢と間隔で受けるようにしましょう。

忙しい現代社会において、胃潰瘍は多くの人々が直面する健康問題の一つです。突然、胃の痛みや胸やけの症状が現れて、「もしかして、胃潰瘍では?」と不安な方がいらっしゃるかもしれません。胃潰瘍の原因としては主にピロリ菌が知られていますが、最近では薬剤による副作用も増えています。健康な生活を取り戻すためにも、胃潰瘍の原因や症状を正しく理解し、適切な治療を受けることが大切です。この記事では、胃潰瘍について、主な症状や原因、適切な検査・診断方法、そして効果的な治療法と予防策までを詳しく解説していきます。
胃潰瘍とは、胃液に含まれる胃酸が胃壁を守る粘膜を傷つけ、一部が欠損した状態になる病気です。胃の粘膜は、粘液によって胃酸や消化酵素から守られています。しかし、何らかの要因で胃酸の量が増えると、強い酸性である胃酸によって、自らの胃の粘膜にダメージを与えてしまうのです。胃の壁は内側から粘膜層・粘膜下層・固有筋層・漿膜層の順に4層で構成されています。損傷が粘膜層で留まっている傷が浅いものを「びらん」、損傷が粘膜下層よりも深いものを「潰瘍」と言います。
胃潰瘍にはさまざまな症状があります。ここでは主な症状として、痛み・不快感・下血とに分けて説明します。
胃潰瘍を発症すると特有の痛みが現れます。主に空腹時や食後に、上腹部やみぞおちに鈍い痛みを生じます。胃の背中側のあたる部分に痛みが出ることもあり、人によって痛みの程度は異なります。
胃潰瘍により、胃もたれや胸やけ、げっぷ、食欲不振、吐き気や嘔吐などの不快な症状が起こることがあります。
胃潰瘍が悪化すると、潰瘍から出血が起こり、吐血や便に血が交じる黒色便(タール便)などの症状が見られることがあります。便が黒くなるのは、出血した血液が胃酸の影響を受け、ヘモグロビン中の鉄が酸化して便に混じるためです。胃から肛門までは距離があり、通過時間が長くなるため便が真っ黒になります。出血が続くと貧血を引き起こすことがあるので注意が必要です。ほかの自覚症状がない場合でも早めに受診することをおすすめします。
胃潰瘍になる原因として、以前はピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)が多かったのですが、現在は薬剤が原因となるケースが増えてきています。ストレスが胃潰瘍の原因になるともいわれていますが、日常に受ける程度のストレスであれば、潰瘍レベルにまでになるケースはほとんどありません。ここでは胃潰瘍の主な原因について説明します。
胃潰瘍の主な原因の一つがピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)という胃の中に生息している細菌です。ピロリ菌は乳幼児期に主に親子間での口移しで与えた離乳食や水などを介して感染することが多いとされています。ピロリ菌は、適切な薬物療法により除菌が可能です。
近年、胃潰瘍の原因として特に増加しているのが、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や抗血小板薬、抗凝固薬(抗血栓薬)の副作用です。NSAIDsは痛みを和らげたり、炎症を抑えたりする薬ですが、服用によって胃の粘膜が傷つきやすくなり胃潰瘍を引き起こすことがあります。また、狭心症や脳梗塞の予防や治療のために処方される抗血小板薬や抗凝固薬も、NSAIDsと併用することで出血や潰瘍発症リスクが高まります。
喫煙、アルコール、暴飲暴食、塩分の多いものや脂っこいもの、刺激物の過剰摂取は、胃酸の過剰な分泌を招き、胃潰瘍のリスクを高める原因となります。

胃潰瘍を疑う場合、主に胃X線検査(バリウム検査)と内視鏡検査(胃カメラ)をおこない診断します。それぞれの検査の特徴と、胃潰瘍の主な原因であるピロリ菌の有無の検査についても解説します。
バリウム(造影剤)と発泡剤を飲み、胃を膨らませて検査をおこないます。胃の壁にバリウムを付着させ、そこにX線を当てて、胃壁の凹凸を観察する方法です。異常を発見した場合は、内視鏡検査でより詳しく検査をすることになります。
メリット
■身体の負担が少ない:体内に器具を挿入しないため、身体の負担が少ない。
デメリット
■精密な診断が難しい:微小な病変を見逃しやすい。
■組織を採取できない:直接組織を採取して詳しく調べることができない。
■被ばく:X線による被ばくがある。
■下剤の服用:バリウムを排泄するために下剤の服用が必要になる。
内視鏡(胃カメラ)を口や鼻から入れて、胃の内部を直接観察する方法です。胃の中を直接観察できるため、胃潰瘍の検査・診断には内視鏡検査が適しています。内視鏡検査では、胃潰瘍の状態や進行度、ピロリ菌感染の有無を確認できます。また、異常があれば組織を採取して病理検査を実施することができます。口からの内視鏡検査であれば、出血がある場合は止血処置も可能です。
メリット
■精度が高い:胃の粘膜を直接観察するため、わずかな潰瘍や病変を見つけやすい。
■組織の採取:その場で組織を採取し詳しい検査ができる。
■治療もできる:出血していた場合、その場で処置ができる。
デメリット
■痛み・不快感:口や鼻からカメラを挿入するため、喉の痛みや不快感、吐き気などがある。
■休憩時間が必要:痛みや不快感を緩和するために、鎮静剤を使う場合は回復にしばらく休憩が必要になる。
西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUの内視鏡検査では、日本消化器内視鏡専門医・指導医の資格を有している医師が担当しています。内視鏡検査の「痛い」「苦しい」といった不安をできるだけ軽減するために、鎮静剤を使ってうとうとしている間に検査を終えることができます。使用している内視鏡は先端部が細く、口からも鼻からも挿入が可能で、高画質カメラで精密に処置できます。その他、病変を見つけると知らせてくれるAIシステムを導入するなど、安心して検査を受けていただけるように工夫しています。

胃潰瘍の主な原因のひとつであるピロリ菌の有無を調べることで、胃潰瘍の予防に役立ちます。会社や自治体の健康診断の際に検査を受けることも推奨されています。ピロリ菌検査には、内視鏡を使う方法と使わない方法があります。
≪内視鏡を使わない検査≫
内視鏡を使わずに、吐いた息や血液、尿、便などからピロリ菌を調べる方法には次のようなものがあります。
■尿素呼気試験
尿素の薬剤を口から投与し、その後、吐いた息のなかの二酸化炭素の量からピロリ菌の有無を確認します。
メリット
負担なく短時間で検査でき高精度。内視鏡を使わない検査の中では、最も信頼性が高い。
デメリット
プロトンポンプ阻害薬(胃液の分泌を抑え胃潰瘍などを治療する薬)などを服用している場合、偽陰性(感染しているのに、陰性と判定されること)となる可能性がある。
■抗体測定
血液や尿を採取してピロリ菌に対する抗体があるかを確認します。
メリット
■血液や尿から簡便に検査できる。
デメリット
■除菌が成功しても抗体は一定期間残るため、陽性と判定されることがある。
■便中抗原測定
便の中にあるピロリ菌の抗原を調べます。
メリット
■精度が高く、除菌前後の判定に用いられる。
デメリット
■便を採取する必要があるため抵抗感のある方にはストレスになる。
≪内視鏡を使う検査≫
胃内視鏡検査で胃の粘膜の組織を採取し、ピロリ菌の有無を確認する方法には以下のようなものがあります。
■迅速ウレアーゼ試験
胃の組織と試薬を反応させて、ピロリ菌が作る酵素(ウレアーゼ)による色の変化を調べます。
メリット
■検査時間が短く迅速に結果が出る。
■試薬の色の変化を見るだけなので、判定が簡単。
デメリット
■プロトンポンプ阻害薬(胃液の分泌を抑え胃潰瘍などを治療する薬)などを服用している場合、偽陰性と判定されることがある。
■鏡検法
胃の組織を染色しピロリ菌がいるかを顕微鏡で確認します。
メリット
■炎症の強さや、がん細胞の有無などについても診断できる。
デメリット
■ピロリ菌の量が少ないと判定が難しいことがある。
■培養法
胃の組織をピロリ菌が発育しやすい環境で培養し、ピロリ菌の有無を調べます。
メリット
■特異度が高い(感染していない場合、陰性と正しく判定できる可能性が高い)
■培養したピロリ菌を使ってどの薬が効果的かを調べることができる。
デメリット
・結果がでるまでに5~7日程度かかる。
・感度が高くない(感染しているのに、陰性と判定される可能性がある)。
胃潰瘍の治療方法は、まずは胃液の分泌を抑えることが基本です。ピロリ菌を保有している場合は除菌治療をおこないます。また、胃酸の分泌を抑える薬剤の服用や生活習慣の見直し、出血が見られる場合は内視鏡で止血するなどの対策も必要です。以下で詳細を説明します。
ピロリ菌を除去する抗菌薬とその効き目をよくするために、胃酸の分泌を抑える薬剤を1週間服用します。この段階で多くの場合は除菌することができますが、できなかった場合は異なる薬剤を用いて除菌を試みます。胃潰瘍の原因が服用中の薬剤の副作用の場合、疾患治療のためにその薬剤の中断が難しい場合は、できるかぎり中止せずに治療を進めることが重要です。
ピロリ菌に感染していない場合は、胃酸の分泌を抑え、胃の粘膜を保護するための薬剤(防御因子増強剤薬)により症状の改善を図ります。また、胃酸の分泌を促すコーヒーや紅茶、強い香辛料や消化に負担がかかる脂肪や繊維の多い食品を避け、食べ過ぎや不規則な食事時間にならないように注意します。その他、喫煙やアルコールを控える、適度な運動をする、過労やストレスを避けるなど、生活習慣全般の見直しが大切です。
胃潰瘍が進行し下血が起きている場合、内視鏡手術によって出血を止める治療をおこないます。止血方法としては、熱凝固による方法、クリップで出血している血管や粘膜を圧迫する方法、薬剤を直接注射する方法があり、出血部位や出血量などの状態を考慮し適切な方法を選択します。
消化性潰瘍の多くはピロリ菌が原因です。そのため、ピロリ菌を保有しているか検査をし、保有していることがわかれば、早めに除菌治療をおこなうことが、胃潰瘍の予防方法として有効です。また、潰瘍発症の原因となる非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)を服用している場合は、できるだけ副作用を避けるため、空腹時に服用しない、用法・用量を守り、1回あたり、あるいは1日あたりの用量を超えないように注意することが重要です。
暴飲暴食を避け、胃の粘膜に負担をかけるような刺激物を避けるなど、食生活を見直すことも大切です。
胃潰瘍の原因の多くはピロリ菌や薬剤による副作用です。ピロリ菌に感染していても自覚症状はほとんどないため検査が必要です。
胃潰瘍は放っておくと傷が深くなり胃の壁に穴があくリスクがあります。腹膜炎を発症すれば、緊急手術が必要になる場合があるため、みぞおちの痛みや胸やけなど、何らかの症状が見られたら、早めに医療機関を受診することが大切です。
西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUは、身体への負担をできる限り抑えた低侵襲外科治療を専門的におこなう病院です。胃潰瘍の検査に欠かせない内視鏡検査は、消化器内視鏡専門医・指導医資格を持つ経験豊富な内視鏡医が担当します。検査時には鎮静剤を使用するため、うとうとしている間に終えることができます。胃の症状に不安がある方やピロリ菌の検査をしたい方はいつでもご相談ください。

腹痛や下痢は、ごく一般的に起こる症状のひとつです。暴飲暴食など、腹痛や下痢の原因が思い当たる場合や、体質などと思っている方も多く、症状が軽い場合にはあまり気にしていない方もいることでしょう。ただし、症状が急で激しい場合には、重症化のリスクや深刻な病気が隠れている可能性があるため、注意が必要です。このような場合には、すぐに病院で診察を受ける必要があります。ここでは、腹痛と下痢が同時に起こる原因や、自分でできる対処法を紹介し、腹痛や下痢を生じる病気について詳しく解説します。
1.腹痛と下痢を同時に引き起こす原因
食事をすると、胃や十二指腸で消化され、小腸や大腸を通過する間に、必要な栄養素は水分と一緒に吸収され、不要なものは適度な硬さの便となり排泄されるのが通常です。下痢は、便の水分量が多い状態で、腸管で水分が吸収しきれなかったり、腸からの水分の分泌が増えたりした場合に起こります。また、下痢の時には、腸の収縮やけいれん、炎症などにより腹痛をともなうことがあります。
腹痛と下痢が同時に引き起こされる原因を、次の4つに分けて説明します。
腹痛と下痢は、食べ過ぎや飲み過ぎ、食中毒や感染症など、食事と関係して起こることがあります。
■食べ過ぎ・飲み過ぎ
食べ過ぎると消化不良になることがあり、消化できていない食物が腸を刺激することで腸の動きが速くなり、本来、腸で吸収される水分が吸収されないまま便と一緒に排出されて下痢になります。過度の飲酒や刺激物の摂りすぎなども、腸を刺激する原因となり、腹痛や下痢を起こすことがあります。
■食中毒などの感染性の下痢
ノロウイルスやO-157などのウイルスや細菌が付着した食物を摂ると、病原体が消化管で増殖し、腸などを傷つけたり炎症を起こしたり毒素を出したりします。生体防御反応として、これらの有害物質を排出するために腸からの分泌物を大量に増やすため、水様性の下痢になり腹痛をともないます。
腸の動きは自律神経の働きが大きく関わっており、脳が強いストレスや緊張を感じると、自律神経を刺激して腸の動きが異常に活発になります。そのため、便が腸を通過するスピードが早くなり、水分を吸収しきれずに下痢になります。また、脳と腸は互いに連携していることもわかっており、腸の異常を脳が感知することで、腹痛を強く感じるようになります。
体が冷えると胃腸の血管が収縮して血流が減るため、胃腸の働きが悪くなって消化不良になりやすいことや、冷えによって自律神経がバランスを崩すことなどが関わって、下痢を引き起こす原因となります。
また、生理中の下痢は、生理周期におけるホルモン分泌と関係しています。生理中は子宮内膜からプロスタグランジンという物質が分泌され、子宮を収縮させて経血を押し出す働きがあり、月経痛の原因となります。同時にプロスタグランジンは、腸管に対しても異常に収縮させるため、腹痛をともなう下痢が引き起こされるのです
腹痛と下痢が同時に起こる原因が、消化管の病気であることがあります。中には、手術など緊急の処置が必要な病気もあります。腹痛と下痢から病気を診断するには、画像診断や血液検査などが必要になる場合がありますが、医療機関を受診する際には、以下のことを伝えるようにしましょう。
■医療機関を受診する際に伝えるポイント
■どのような症状が、いつから始まり、どのぐらい続いているか
■排便の頻度と便の状態
■腹痛の有無とその程度
■腹痛と下痢以外の症状の有無
■発症前後の状況(食事、生活、薬、サプリメントなど)
■基礎疾患の有無(服用している薬など)
腹痛と下痢がある場合の自宅でできる対処法について説明します。ただし、腹痛と下痢が同時に起きており、発症や症状の経過が急である、症状が強く激しいなどの時には、以下の点に注意したうえで、医療機関を受診しましょう。
どのような下痢であっても、最も大切なのは脱水にならないように、しっかり水分を摂ることです。スポーツドリンク、経口補水液など電解質が含まれた飲料を、少しずつ飲むようにします。おかゆ、重湯、柔らかく煮たうどん、みそ汁、野菜スープなど、食事から水分を摂ることも大切です。
緊張やストレスがあるとお腹が痛くなり下痢になるなど、一定の条件で症状が発症することが分かっている場合には、下痢止めが有効な場合があります。しかし、むやみに下痢止めを使うことはすすめられません。それは、腹痛と下痢の原因が、食中毒や感染症の場合、病原体を排出するために下痢が起きているからです。また、一時的に腹痛や下痢を止めてしまうことで、症状の原因となる消化管の病気の発見が遅れることがあるからです。下痢止めはさまざまな種類があるため、医療機関や薬剤師に相談して、適切に使用することが大切です。
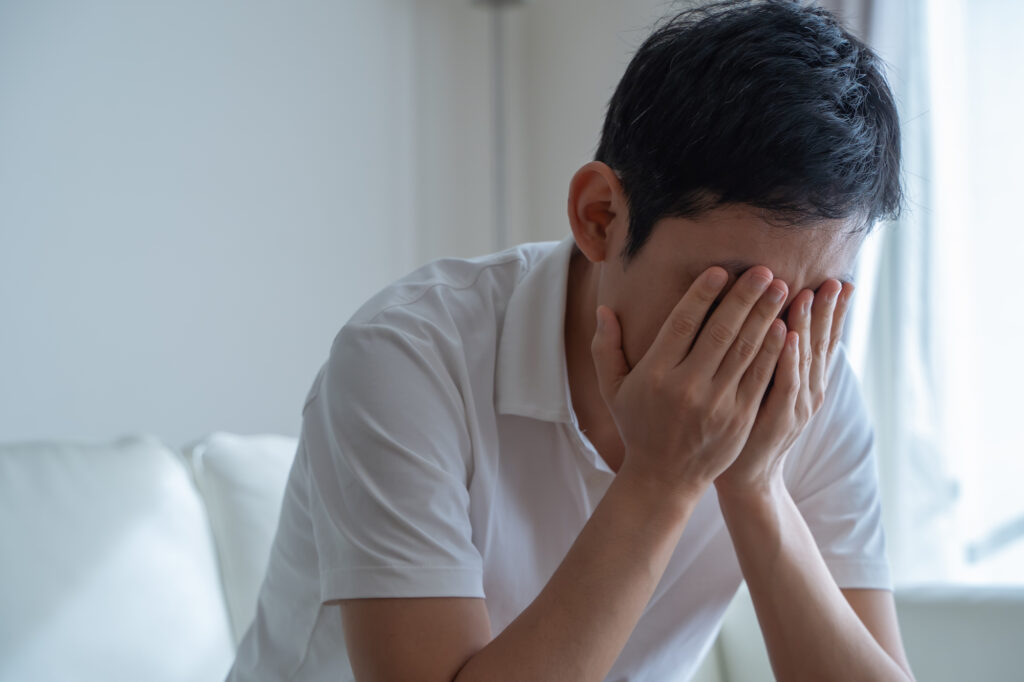
腹痛と下痢が同時に起こる際に疑われる病気について、以下に病気の概要、原因、症状について説明します。
急性胃炎・腸炎は、何らかの原因で胃や腸に炎症が起きている状態です。
■原因
急性胃炎・腸炎の多くは、ウイルスや細菌、寄生虫による感染が原因の感染性胃腸炎です。感染以外が原因で急性胃腸炎を発症する場合もあり、その原因として暴飲暴食、アレルギー、キノコや貝類による中毒、薬などが挙げられます。
■症状
急性胃炎・腸炎の原因にもよりますが、腹痛、下痢、吐き気、嘔吐、発熱、血便が主な症状です。下痢や嘔吐にともない体の水分が不足して脱水症状となり、口の渇きや倦怠感があらわれ、悪化すると血圧低下や意識障害をおこすことがあるため注意が必要です。
炎症性腸疾患とは、腸の粘膜に炎症を起こす病気の総称で、一般的には潰瘍性大腸炎とクローン病のことをいいます。潰瘍性大腸炎(かいようせいだいちょうえん)は大腸に炎症が生じる一方、クローン病は口から肛門までの消化管すべてに炎症を生じます。いずれも難病に指定されており、良くなったり悪くなったりを繰り返し、長期間の治療が必要な慢性の病気です。
■原因
潰瘍性大腸炎もクローン病も、詳しい発症の原因は解明されていませんが、遺伝的因子と環境因子(腸内細菌叢、ウイルスや細菌などの感染など)が複雑にからみ合い、免疫機能の異常がもたらされることで、発症や炎症の持続に関わっていると考えられています。
■症状
腸の炎症により、共通して下痢、腹痛、血便の症状があらわれます。また、発熱や倦怠感などの全身症状、関節炎、皮疹(ひしん)、結膜炎、口内炎など、腸以外の部位に症状が出ることもあります。特に、潰瘍性大腸炎は、血便(粘液便)と下痢が多く、クローン病は腹痛と下痢、肛門周辺に膿がたまる穴(痔ろう)をともなうことが多いのが特徴です。
何らかの原因で、大腸の動脈への血流が妨げられて、大腸の粘膜に炎症が起きて傷ついている状態です。大腸の動脈への血流が妨げられるのは、血管と腸管の両方に要因があり、それぞれがからみ合って発症すると考えられています。
■原因
大腸の動脈への血流が妨げられる原因として、動脈硬化をきたす糖尿病、高血圧、脂質異常症などの基礎疾患や、血液が固まりやすい方に起こりやすいです。また便秘のある方では、排便の時に強くいきんだことで血流が低下して起こることがあります。
■症状
左側の大腸に起こることが多いため、突然、左下腹部の腹痛の後、軟便や下痢になることがあります。大腸への血流が妨げられることで粘膜が傷つき、潰瘍ができて出血すると血便になります。また微熱が出ることもあります。ほとんどの場合、一時的な症状ですが、腸閉塞や腹膜炎を併発すると手術が必要になることもあります。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、食物を分解する働きのある胃酸や消化酵素によって、胃や十二指腸の粘膜が深く傷つけられて潰瘍になっている状態で、消化性潰瘍とも呼ばれます。
■原因
胃潰瘍・十二指腸潰瘍の原因として、ヘリコバクター・ピロリ菌感染が深く関わっています。ヘリコバクター・ピロリ菌が胃や十二指腸に感染すると、胃や十二指腸の粘膜に慢性的な炎症が生じたり、粘液が減ったりすることで、粘膜が傷つきやすくなり発症します。また解熱鎮痛剤、喫煙、暴飲暴食、ストレスなどにより、粘膜が傷つきやすい状態となり発症する場合もあります。
■症状
胃潰瘍も十二指腸潰瘍も腹痛が主な症状で、みぞおちあたりの鈍い痛みや吐き気、嘔吐をともなうこともあります。胃潰瘍は食後、十二指腸潰瘍は空腹時や夜間に痛みが強くなることが多いようです。いずれも潰瘍から出血すると、黒色の便が出たり、貧血や顔色が悪くなったり、疲れやすいなどの症状をともなうことがあります。
大腸憩室炎とは、憩室と呼ばれる消化管の一部分にできた風船状の小さい袋に炎症が起きる病気です。
■原因
憩室は、大腸にできることがほとんどで、腸壁の弱い部分に圧力が加わってできるといわれています。憩室のある方で、便秘や肥満、喫煙などが憩室炎を発症するリスクとして挙げられます。
■症状
大腸憩室炎の主な症状は、左下腹部の痛み、吐き気、嘔吐、下痢、腹部の圧痛などです。憩室炎が進行し憩室に穴があいたり、膿がたまったりすると、膀胱炎や腹膜炎などを合併することがあります。
検査では大腸の腫瘍や炎症などの病気がないのにもかかわらず、数ヵ月間以上、腹痛が繰り返し起こり、下痢や便秘など便の状態や排便の回数が変わる病気です。お腹の症状や、腹痛や排便に対する不安で日常生活に支障がある場合があります。
■原因
腸の働きは自律神経がコントロールしていますが、脳がストレスや不安を感じると自律神経のバランスが崩れて、腸の動きが異常になり下痢や便秘などの症状があらわれます。それと同時に、腸で生じた異常を脳が感じると痛みに対して過敏に反応するようになり、腹痛が起こりやすくなるということが、過敏性腸症候群の発症メカニズムと考えられています。
■症状
症状の現れ方には個人差があり、下痢型、便秘型、混合型があります。下痢型は、ストレスや不安をきっかけに急な腹痛と便意、下痢を生じます。便秘型は、便秘にともないお腹の張りなどがあります。混合型は、下痢と便秘を繰り返すのが特徴です。ストレスや疲労で症状が悪化し、休日などには症状があらわれにくいようです。
慢性膵炎とは、膵臓に繰り返し炎症が起こることで、膵臓で作られる消化酵素によって、自らの膵臓の正常な細胞が壊され、線維に置き換わり(線維化)、膵臓が働かなくなる病気です。
■原因
慢性膵炎は、男性では主にお酒の飲み過ぎが原因であり、女性では原因の分からない特発性膵炎が多くみられます。また、喫煙は発症リスクとなることが分かっています。
■症状
初期の主な症状は腹痛で、食後数時間で現れることが多く、吐き気や嘔吐、上腹部の膨満感をともなうことがあります。進行すると徐々に膵臓の機能が低下して、消化不良による下痢、体重減少が起こります。また、膵臓の機能のひとつである血糖を下げるインスリンの分泌が低下することで、糖尿病によるのどの渇き、夜間の頻尿や多尿などの症状があらわれます。
腹痛と下痢が同時に起こっている場合に、手術などの緊急治療が必要な病気があります。また、胃がんや大腸がんのように、腹痛と下痢はもちろん、自覚症状がある場合には進行している可能性が否定できず、早急に検査を受け、診断と治療をはじめる必要があるものもあります。腹痛と下痢が同時に起こった場合に、早急な診断と治療が必要な病気について、原因や症状を紹介します。
腸閉塞とは、何らかの原因で腸の内容物が肛門の方に移動できなくなっている状態です。腹部の手術経験のある方は注意が必要です。
腸の内容物が肛門の方に移動できなくなる原因として、腹部の手術後に腸管が狭くなったり、腸捻転(ちょうねんてん)やヘルニアなどによって腸管が折れ曲がったりして起こる通過障害や、腹部の手術にともなう腸管の麻痺やけいれんで腸が動かなくなることです。
腸閉塞の症状の特徴は、腹痛、嘔吐、便やガスが出なくなることです。ただし、部分的な閉塞の場合や、腸閉塞の初期には、閉塞している部分よりも肛門側にある便が、腸の強い蠕動運動(ぜんどううんどう)によって下痢となって出ることがあります。そのほか、腹部膨満感(ふくぶほうまんかん)や食欲不振をともなうこともあります。腸管の血流が悪くなって起こる絞扼性(こうやくせい)イレウスは、強い腹痛に発熱、嘔吐をともない、腸管の血流が悪くなり壊死する場合があるため、診断と治療に緊急性を要します。
胃や大腸の粘膜の細胞が、何らかの原因でがん細胞になる病気です。がん細胞が増えて周囲にしみ出したり、他の臓器に転移したりすることがあります。
■原因
胃がんの原因は、主にヘリコバクター・ピロリ菌の感染に生活習慣のリスクが重なり、胃の粘膜が萎縮して発症することが多いです。大腸がんは、大腸の粘膜にできた腺腫(せんしゅ)と呼ばれる良性のポリープが大きくなりがん化する場合や、大腸の粘膜から直接発生する場合があります。
■症状
胃がんも大腸がんも、初期はもちろん進行しても、ほとんど自覚症状がない場合があります。比較的多く見られる症状も、他の消化器の病気と似た症状で、特有の症状があるわけではありません。胃がんと大腸がんの代表的な症状は次の通りです。
■胃がん
食欲不振、胃の不快感、胃やみぞおちの痛み、吐き気を感じることがあり、腫瘍から出血すると、黒色便や貧血になることがあります。また、進行胃がんやスキルス胃がんでは、がん性腹膜炎や腹水により腹痛や下痢を生じることがあります。
■大腸がん
下血・血便、下痢と便秘を繰り返す、出血による貧血、腹部のしこり、便が細くなる、残便感、腹痛などの症状を生じることがあります。

腹痛と下痢がある場合に、病院で診察を受けた方が良い状態なのか、判断に悩むことがあります。次の症状がある場合には、緊急で医療機関への受診をしましょう。
これまでに経験したことがない、冷や汗が出るほどの耐えられない激しい痛みは、緊急で受診が必要な症状です。例えば、胃や腸に穴が開いた、腸閉塞などの治療が必要な状態の可能性があるからです。
腹痛と下痢に、発熱や吐き気、嘔吐、血便などをともなう場合は、緊急で病院を受診するべき状態です。ウイルスや細菌による感染性腸炎や食中毒が疑われ、脱水のリスクが高く、点滴による水分や電解質の補給、原因物質が分かれば薬物療法など適切な治療が必要だからです。
腹痛が続く場合や、だんだん痛みが強くなる場合も、すぐに病院を受診するべき状態です。なぜなら腹痛の痛みが長時間消えない場合は、緊急性が高く早期の診断や手術などの治療が必要な場合が多いからです。腹痛が持続する時間の目安は6時間以上とも言われていますが、時間に関わらず安静にしていても痛みが続く場合には、急いで病院を受診しましょう。
腹痛と下痢が同時に起こっている場合、通常の検査として、血液検査、尿や便の検査、腹部X線検査をおこない、必要に応じて腹部超音波検査(腹部エコー)、腹部CT検査、腹部MRI検査をおこなうこともあります。さらに精密検査として、大腸カメラ、問診により胃の病気が疑われる場合には胃カメラをおこなうこともあります。
■腹痛や下痢がある時の検査項目
| 主な検査 | 主な検査の項目や診断、検査の目的 |
| 血液検査 | ・白血球・CRP:炎症の存在・好酸球:寄生虫の感染の有無・貧血:出血の有無・電解質の異常:脱水の状態・血糖値、凝固能、脂質など:基礎疾患の確認 |
| 尿検査 | ・尿路系の疾患の推定(尿路感染症など)・妊娠反応 |
| 便の検査 | ・便潜血:潰瘍、びらん、腫瘍などからの出血・便培養:細菌性腸炎など |
| 腹部X線検査 | ・腸管のガスの有無や分布・腸閉塞の有無 |
| 腹部エコー検査、腹部CT検査、MRI検査 | ・膵炎、腸管の拡張、腸管壁の肥厚などの観察・尿路結石、胆石の確認 |
| 大腸カメラ | ・虚血性腸炎、細菌性腸炎などの診断・炎症性腸疾患の診断・大腸の憩室の有無・大腸ポリープや大腸がんの発見 |
| 胃カメラ | ・胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎の診断・胃がんの発見・ヘリコバクター・ピロリ菌感染の有無など |
腹痛と下痢が同時に起こった時、感染性胃腸炎や暴飲暴食など食事に関係している場合があります。感染性胃腸炎では、食物から入り体内で増えた病原体を排出するために腹痛と下痢が起こります。また、暴飲暴食では消化不良や、アルコールの刺激によって腸が激しく動き、腸管で水分が吸収されずに腹痛と下痢が起こります。食事以外の原因として、大腸は自律神経によってコントロールされているため、ストレスや不安が引き金となり、脳と腸が相互に関係して大腸を刺激し下痢と腹痛を生じます。また、女性は生理周期にともない腹痛と下痢になる方も少なくありません。腹痛と下痢が同時に起こった時、最も大切なのは脱水にならないように、水分を適切に摂ることですが、すぐに病院を受診して診断と治療が必要な場合もあるため、自己判断で下痢止めなどを使用せず、症状の強さや経過に注意が必要です。腹痛と下痢が同時に起きる場合に疑われる病気は数多くあり、放っておくと重症化したり、重篤な病気が隠れていたりすることもあります。気になる症状がある場合には、病院を受診して大腸カメラ検査などでその原因を明らかにし、適切な治療をすることが大切です。
西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUでは、最新の内視鏡システムを導入し、可能な限り苦痛の少ない検査を目指しています。検査・治療は、総合病院で経験を積んだ日本消化器内視鏡専門医・指導医の資格を持った医師がおこない、AIによる見落とし防止システムも導入しています。受診当日や土曜日に検査することもできるため、腹痛や下痢の症状にお悩みの方は、是非ご相談ください。

大腸カメラ検査や胃カメラ検査は、食道や胃、十二指腸、大腸などの消化管を直接観察し、さまざまな病気の早期発見や診断に役立つ有用な手段です。「大腸カメラも胃カメラ検査も必要だと分かってはいるけれど、忙しくてなかなか時間をとれない」という方は多いのではないでしょうか。大腸カメラと胃カメラの検査では、検査前の食事制限や検査の流れが共通しているため、医療機関によっては同じ日に受けることが可能です。この記事では、大腸カメラと胃カメラの同日検査のメリットや注意点、検査の流れについて、詳しく解説します。
大腸カメラ検査と胃カメラ検査を同じ日に受けることは可能です。どちらの検査にも食事制限や時間的な拘束、投薬が必要ですが、2つの検査を同じ日におこなうことで、それらの負担をまとめることができます。ただし、高齢の方やハイリスクな病気を抱えている方は、身体の負担を考慮して、別の日に実施をおすすめする場合があります。
大腸カメラ検査と胃カメラ検査を同じ日に受けるメリットについて、スケジュール調整、費用、食事制限の回数の観点からご紹介します。
2.1. スケジュール調整の負担が減る
大腸カメラと胃カメラの検査を別の日に受ける場合、それぞれに事前受診、検査、結果説明のための受診が必要になります。2つの検査を同じ日に受けることで、これらの受診が半分で済み、スケジュール調整の負担が軽くなります。それぞれの診断結果を早く知ることができる点もメリットです。
2.2. 費用総額が安くなりやすい
2つの検査を別の日におこなうよりも、費用総額が安くなりやすくなることもメリットです。例えば、検査に関わる初診料や再診料、薬代、検査で使用される麻酔薬(鎮静剤)の料金など、2つの検査で重複している費用が節約できる可能性があります。また、検査日が同じ日になることで、来院回数が減るため、交通費の負担も抑えられるでしょう。
2.3. 食事制限が1回で済む
大腸カメラ検査や胃カメラ検査は、検査前に食事制限が設けられます。例えば、前日は21時までに夕食を終え、当日の朝は絶食する必要があるなど、検査に向けて事前に食事を調整しなければなりません。検査が別の日におこなわれる場合には、こうした食事制限が2回必要になります。しかし、2つの検査を同じ日におこなうことで、食事制限は1回で済み、時間と手間が軽減されます。これは特に忙しい方にとってはメリットといえるでしょう。

大腸カメラと胃カメラの検査を同じ日に受ける際の注意点について、副作用の可能性、実施可能な病院の少なさの観点からご紹介します。
3.1. 体質によっては麻酔の副作用が起こる可能性がある
大腸カメラと胃カメラの検査を同じ日におこなうことで、単独でおこなうよりも検査時間は長くなります。その分、検査中に使用する麻酔薬(鎮静剤)の量が増加するため、患者さんの体質によっては、血圧の低下や呼吸が弱くなるなどの副作用が生じる可能性があります。
3.2. 実施可能な病院を見つけることが難しい
大腸カメラ検査と胃カメラ検査を同じ日におこなう場合、検査時間が長くなるため、麻酔薬(鎮静剤)の適切な調整が求められます。そのため、高度な内視鏡挿入技術や麻酔薬(鎮静剤)の管理が必要になり、実績豊富な病院で熟練した医師やスタッフによる対応が求められます。このような条件を満たす病院は限られているため、同じ日に胃カメラ検査と大腸カメラ検査を受けられる病院を見つけるのが難しいといえるでしょう。
大腸カメラと胃カメラを同じ日におこなう場合、どのような流れで実施されるのでしょうか。検査の流れについては病院やクリニックによって異なります。ここでは、西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKU の同日検査について詳しく解説します。
4.1. 前日・当日の食事について
大腸に便や未消化の物質が残っていると、検査に時間がかかり正確な診断ができなくなります。できる限りスムーズな検査ができるように、検査の前日は消化に良いもの(素うどんやおかゆ、豆腐、たまご、やわらかく煮た大根や人参、プリン、ゼリーなど)を食べるようにおすすめしています。消化に悪いもの(ゴボウや葉野菜、トマト、ゴマ、とうもろこし、海藻類、ひじき、切り干し大根、こんにゃく、納豆など)は避けるようにしましょう。西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUでは、検査前日の夕食は21時までに済まし、それ以降は、水分を除き当日の検査終了まで絶食としています。
4.2. 着替え・検査前のお薬の服用
大腸カメラ検査のために、検査前日の寝る前に下剤を服用し、当日も検査の5時間前から下剤の服用を開始します。(便が透明な状態であることを確認します。)来院したら検査着に着替えます。胃カメラ検査のために、胃の中の泡をとるための薬を服用します。鼻から内視鏡を入れる方は、鼻の粘膜を広げる点鼻薬を投与します。喉をしびれさせる麻酔薬の入った氷を口にふくんでいただきます。必要に応じて追加のスプレー麻酔をします。
4.3. 血圧・脈拍モニターを装着し麻酔
ベッドに横になり血圧計や脈拍モニター、酸素モニターを装着します。大腸カメラ検査、胃カメラ検査のどちらが先の場合も、左側を下にして横になります。口から胃カメラを挿入する方は、マウスピースをくわえます。(鼻から検査をする方は鼻の麻酔をします。)その後、鎮静剤(眠くなる薬)を点滴で投与し検査に入ります。(西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUでは、大腸カメラ検査を受ける場合、原則鎮静剤を使用させていただきます。)
4.4. 胃カメラを挿入
胃カメラを挿入します。西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUで使用する胃カメラは、先端部が径5.8mmの、高画質細径カメラで、鼻もしくは口から挿入可能です。食道・胃・十二指腸の内視鏡治療には先端部径9.8mmの処置用スコープを使用します。どちらも、操作性に優れ、画質が良く、より精密な処置が可能です。
また、AI内視鏡システムを導入しており、病変がある場所をAIが表示します。検査の所要時間は7~8分程度で、検査中は常に血圧や脈拍をモニターで観察し、異常があればすぐに対応できる体制を整えています。
4.5. 大腸カメラの挿入
ベッドの方向を180度回します。左側を下にしたまま、膝を抱えるような姿勢になり、大腸カメラがスムーズに動くように肛門に麻酔ゼリーや潤滑用ゼリーを塗ります。肛門から大腸カメラを挿入します。この際も必要があれば鎮静剤を追加して投与します。大腸カメラは、先端径11.7mmの高画質カメラで、ポリープの診断に欠かせない拡大観察機能を併せ持っています。病変はAIが検出して表示する仕組みです。大腸カメラ検査の所要時間はおよそ、10分~20分程度です。
4.6. リカバリー室での休憩
検査後は、リカバリー室(休憩室)に移動し、ベッドで30分~1時間程度、ゆっくりお休みいただきます。リカバリー室でも血圧と血中酸素量のモニターで観察をしているので安心です。目が覚めたら、着替えをしていただきます。
4.7. 結果のご説明
当日、結果説明をご希望の方は、診察室で検査画像をみながら、一緒に確認しご説明します。
病理検査をおこなった場合は、結果が出るまで2週間ほどかかるので、後日、説明いたします。生検が必要だった場合は、病理検査結果がでる頃に再度受診をしていただいております。
西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUでは、大腸カメラや胃カメラ検査の身体的負担をできるだけ軽減できるように徹底しています。安心して検査をしていただくための当院の検査の特徴についてご紹介します。
5.1. 検査時にかかる身体的負担を徹底的に軽減
大腸カメラや胃カメラ検査は「痛い」「苦しい」というイメージがありますが、西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUでは鎮静剤(麻酔薬)を用いて、うとうとしている間に検査を終えることができます。また、大腸カメラ検査で腸内菅を膨らませる際、空気の代わりに炭酸ガスを用います。炭酸ガスは腸管内で速やかに吸収されるため腸内に空気が長時間残らず、検査後のお腹の張りや痛み、違和感を和らげます。
5.2. ポリープが見つかった場合は治療に移行
西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUは病院施設のため、大腸カメラ検査中にポリープが見つかった場合、大きさが概ね2cm未満で出血のリスクが高くないものについては、そのまま治療に移行し検査中に切除しています(日帰り手術)。また、2cm以上の大きなポリープや早期がんを疑う病変は、別日に短期入院治療をおこなっています。
大腸カメラや胃カメラ検査は、「痛い」「苦しい」「我慢」といったイメージを持たれる方がいらっしゃいますが、内視鏡検査は、病変の早期発見や何らかの症状があるときの診断に有用な手段です。細いスコープや鎮静剤(麻酔薬)の使用、高い内視鏡技術により、なるべく苦痛の少ない検査を目指すことができます。また、大腸カメラと胃カメラを同日に検査することで、食事制限や受診回数、麻酔薬や鎮静剤の投薬回数を減らすことができ、時間的、身体的な負担を軽減できます。
西宮敬愛会病院の低侵襲治療部門COKUは、身体への負担をできる限り抑えた低侵襲外科治療を専門的におこなう病院です。内視鏡部門では、消化器内視鏡専門医・指導医資格を持つ経験豊富な内視鏡医が、最新のシステムと高い挿入技術を用いて検査をおこなうため、大腸カメラ検査と胃カメラ検査を同じ日におこなうことも可能です。また検査時には鎮静剤(麻酔薬)を使用することで、患者さんの苦痛を和らげるよう努めています。大腸カメラ検査や胃カメラ検査に関する不安なことがございましたら、いつでもご相談ください。

胃痛は日常生活に支障をきたす場合があり、繰り返す場合は心配です。健康な胃では胃酸と粘液のバランスが保たれていて、これが崩れると胃粘膜が傷つき胃痛が起こります。痛む部位や痛みの出方はさまざまで、他の臓器に病気が見つかることもあります。胃痛の原因や考えられる病気を中心に検査方法、改善策について詳しく解説します。
胃痛は、胃の攻撃因子である胃酸と、防御因子としての粘液の分泌バランスが崩れることで発生します。通常、胃は粘膜で覆われており、胃酸(主に塩酸)が食べ物の消化と殺菌をおこないますが、同時に胃の粘膜を攻撃します。これに対抗するため、防御因子である粘液が胃粘膜を保護します。攻撃因子と防御因子のバランスが取れていると健康が維持されますが、ストレスや睡眠不足、暴飲暴食、脂肪や刺激物の多い食生活、喫煙などでこのバランスが崩れると、胃酸が粘膜を傷つけ、胃痛が起こります。
また、アニサキスのような寄生虫に対するアレルギーも、胃痛を引き起こす要因です。
胃痛といっても、胃痛を起こした原因や病気によってその症状はさまざまです。例えば、キリキリする痛み、しぼられるような痛み、鈍痛、みぞおち付近の痛み(心窩部痛:しんかぶつう)などです。また、胃痛には、次のような症状をともなうことがあります。
・食欲不振
・膨満感
・胸やけやげっぷ
・吐き気
・吐血や下血
胃痛のよくある原因として、ストレス、食生活、細菌やウイルスの感染、ヘリコバクター・ピロリ菌について取り上げて説明していきます。
攻撃因子の胃酸と防御因子の胃粘液の分泌には、自律神経が関わっています。
ストレスがかかると緊張状態が続くため、自律神経のうちの交感神経が高まり、胃の血管が収縮して血流が低下し、胃粘液の分泌が少なくなります。そのうえ、副交感神経の働きで胃酸の分泌が増えることがわかっています。つまり、ストレスがかかると、攻撃因子と防御因子のバランスが崩れるため、胃粘膜が傷つきやすい状態になることが、ストレスで胃痛が起こる原因です。
胃痛は普段の食生活と深いかかわりがありますが、胃痛のリスクとして、次のような食生活があげられます。
刺激物は、攻撃因子として胃の粘膜を直接傷つけたり、胃酸の分泌を増やしたりするため、胃痛の原因となります。例えば、香辛料の多い激辛のラーメンやカレー、カフェイン飲料やコーヒー、熱すぎたり冷たすぎたりする食べ物などです。
脂肪は胃では消化されずに十二指腸に送られますが、十二指腸で消化を助けるために分泌される消化管ホルモンは、胃の動きを抑える働きがあります。そのため脂肪分の多い食事をすると、食べ物が胃内に留まる時間が長く、胃に負担がかかるため、胃痛の原因となります。
アルコールは、直接胃粘膜に刺激を与えたり、胃酸の分泌を促したりすることから、胃痛の原因となります。
細菌やウイルスは感染性胃腸炎の原因となり、胃痛のほか、腹痛、悪心・嘔吐、下痢、発熱などの症状をともなうことがあります。感染性胃腸炎を起こす原因の病原体によって、症状や治るまでの期間などは異なります。
ヘリコバクターは、胃の粘膜内に生息する細菌のひとつで、感染があると胃の粘膜に慢性的な炎症を起こします。その結果、長い間に胃粘膜に特徴的な変化(萎縮:いしゅく)が起こり、胃粘液の分泌が減ることで、胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がんなどの病気の原因となり、胃痛や胃の不快感などの症状が起こります。ヘリコバクターは、幼少期に保菌者の親から感染し、無症状のまま保菌することが多く、検診や胃カメラで感染が分かった場合には除菌が必要です
胃痛が起きた場合、胃そのものに病気がある場合だけでなく、胃の周辺の臓器に病気がある場合もあります。胃痛が起きた場合に原因として考えられる主な病気を紹介します。

急性胃炎とは、胃の粘膜に急に炎症が起きている状態です。
突然胃が突然キリキリと痛み、吐き気や嘔吐、下痢などの症状をともなうこともあります。
痛み止めなどの薬の副作用、ストレス、激辛など刺激の強い食べ物、アルコールの飲み過ぎなどのことが多いようです。
通常、絶食や消化の良い食物で胃の安静を保つと症状は改善します。胃の粘膜を保護する薬を使うこともあります。
食中毒は、細菌やウイルスなどの微生物が付着した食物を食べることで発症する病気です。
胃痛・腹痛、悪心・嘔吐、下痢・血便のほか、発熱や頭痛など全身症状があらわれることもあります。
肉や魚の生食や不十分な加熱、食品の不適切な温度管理や、原因物質が付着した手指による調理による料理を食べることで起こることが多く、食中毒の原因菌としては、サルモネラ菌、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌(O-157など)、腸炎ビブリオ、ノロウイルス、黄色ブドウ球菌などが知られています。
食中毒が疑われる場合には、下痢止めや胃腸薬などを勝手に飲まずに、医療機関を受診することをおすすめします。医療機関では、食中毒の原因に合わせた治療と解熱剤などの対症療法、点滴による水分と栄養の補給がおこなわれます。
逆流性食道炎は、胃酸や胃の内容物が食道に逆流することで、食道の粘膜に炎症が起きる病気です。
すっぱいものが上がってくる呑酸(どんさん)、胸やけ、食後の胸の痛みなどが主な症状です。寝ている間に逆流すると、せき、のどのかすれや違和感などを生じる場合があります。
食道と胃のつなぎ目の下部食道括約筋(かぶしょくどうかつやくきん)が、加齢による筋力低下、肥満や妊娠による圧迫、食べ過ぎなどにより緩むことが原因です。
生活習慣の改善や肥満の解消を心がけ、胃酸の分泌を抑える薬や、胃の動きを良くする薬などで治療します。
胃・十二指腸潰瘍は、胃や十二指腸の粘膜に潰瘍ができる病気です。
潰瘍のできた部位によって異なりますが、上腹部やみぞおちの鈍痛や吐き気などが主な症状です。胃潰瘍は食後、十二指腸潰瘍は夜間や空腹時に痛みが出ることが多いとされ、吐血や下血がある場合もみられます。
ヘリコバクター・ピロリ菌感染、解熱鎮痛薬、喫煙、ストレスなどが原因で、胃の防御因子が減り、胃から分泌される胃酸や消化酵素によって、粘膜にできた傷が深くなり発症します。
胃カメラで診断し、出血箇所を見つけた場合には、その場で処置具を使って、電気メスでの焼灼やクリップなどで止血することもできます。胃酸の分泌を抑える薬や、胃の粘膜を保護する薬を服用するだけでなく、食生活やストレス解消、禁煙など生活習慣の改善も必要です。
ディスペプシアとは、腹部膨満感、胃痛などみぞおち付近の不快な症状を言いますが、これらの症状があるにもかかわらず、胃カメラやX線検査などで胃がんや胃潰瘍など、症状の原因が見つからない病気です。
慢性的な、胃もたれ、腹部膨満感、胃痛などみぞおち付近の不快な症状があります。
胃や十二指腸の動きが悪くなることや、胃酸に対して痛みを感じやすくなる胃の知覚過敏、ストレスなど、いくつかの要因が複合的に関わって発症します。ヘリコバクター・ピロリ菌が関係していることもあります。
生活習慣や食習慣を改善すると、症状が改善することがあります。薬物療法としては、胃酸の分泌を抑える薬と胃の運動を良くする薬、胃の動きや不安感を和らげる漢方薬を服用することがあります。効果がない場合には、抗不安薬や抗うつ薬を使うこともあります。
胃がんは、胃の内側の粘膜の細胞が、何らかの原因でがん細胞になり、無秩序に増えていく病気です。
初期には症状がないことが多いですが、進行すると、胃痛、胃周辺の不快感・違和感、胸やけ、吐き気、食欲不振などの症状があらわれます。がんが大きくなると、胃粘膜の下層へ深く進み、周辺の他の臓器へも広がり、血液の流れにしたがって、離れた臓器に転移することもあります。
胃がんのリスクとして、ヘリコバクター・ピロリ菌感染、喫煙、塩分の摂りすぎが挙げられます。
胃カメラで胃がんが疑われる細胞を採取し、病理診断をおこない、病期などに合わせた治療法が選択されます。
胆石症は、胆のうや胆管に石(胆石)ができる病気です。約8割は胆のう内に石ができる胆のう結石であり、約2割は胆管に石ができる総胆管結石です。肝臓の中にできることもありますが、ごくわずかです。
食後まもなく、右の肋骨の下あたりや、みぞおちにあらわれる痛みを、胃痛と感じることがあります。右肩に抜けるような痛みが出たり、吐き気や嘔吐をともなったりすることもあります。胆石ができる場所によって、胆汁の流れが悪くなると皮膚が黄色くなる黄疸になります。ただし、胆石症になっても症状がない場合も多く、胆のう結石では約8割の方が無症状です。
胆汁の成分が、何らかの原因で固まって胆石ができることが原因です。胆汁の成分であるコレステロールやビリルビンは、高カロリー食、肥満、脂質異常症、妊娠などに影響を受けることがわかっています。
胆のう結石は、無症状の場合には経過観察をし、症状がある場合は、基本的に手術で胆石と胆のうを一緒に切除します。総胆管結石は症状がある場合が多く、重症になることが多いため、胃カメラや手術で切除します。
膵炎には、急性膵炎と慢性膵炎があります。急性膵炎は、何らかの原因で本来食べ物を消化する膵液によって、膵臓自体の組織が破壊される病気です。慢性膵炎は、膵臓に長期間にわたり炎症が持続することで、膵臓の組織が変化(線維化:せんいか)し、機能が衰える病気です。
急性膵炎の症状は、みぞおちから背中にかけての強い痛み、嘔吐や発熱です。慢性膵炎は腹痛が主な症状で、進行して膵臓がほとんど機能しなくなると、消化不良や下痢が起こることがあり、糖尿病を発症することもあります。
急性膵炎も慢性膵炎も、その原因のほとんどは、長期間に渡る多量の飲酒です。急性膵炎は胆石が原因の場合もあります。
急性膵炎の治療は、絶飲食をし、膵液の働きを抑える薬や痛みに対する鎮痛薬を使用します。慢性膵炎の治療は、膵臓の機能がどのぐらい保たれているかという病期によって異なりますが、禁酒、禁煙に膵液の働きを抑える薬や鎮痛薬を使います。
急性虫垂炎は、いわゆる盲腸です。大腸のもっとも奥の盲腸の部分にある、親指大の突起物の虫垂に、炎症が起きる病気です。
盲腸というと、右下腹の痛みのイメージですが、初期には食欲不振、へその周りの不快感、みぞおちの痛みがあり、胃腸炎の症状と似ています。その後、右下腹部に痛みが集中するように移動します。腹膜炎を併発すると、発熱、下痢、嘔吐をともなうことがあります。
虫垂に硬い便が詰まったり虫垂の粘膜が腫れたりすると、虫垂の出口がふさがることがあります。その結果、虫垂の粘膜の血流が悪くなったり、血の塊ができたりしたところに、細菌が感染すると虫垂に炎症が起こり発症します。
虫垂の炎症の程度や腹膜炎の併発の有無などにより、治療方法は異なります。治療には抗生物質で虫垂の炎症を抑える方法と、虫垂を手術で切除する方法があります。
魚介類に寄生するアニサキスという寄生虫が、胃の粘膜に食い付くことで胃痛が起こる病気で、近年、増えています。
魚介類を刺身など生食で食べた6〜12時間後に、強い胃痛、吐き気、嘔吐などの症状が起こり、蕁麻疹などのアレルギー症状をともなうこともあります。
アニサキスが寄生している魚介類を生食し、胃の粘膜に食いつくことが原因です。胃痛は、アニサキスが食いついた痛みではなく、アニサキスという異物やアニサキスの分泌物に対するアレルギー症状によるものです。
胃カメラでアニサキスが確認できれば、同時に器具を使ってアニサキスを除去する治療をします。胃痛の前に生魚などを食べていれば、早急に胃カメラによる除去がすすめられます。
胃痛が起こる病気がある場合には、その治療が優先されますが、ここでは、日常生活の中でできる胃痛が起きた時の改善方法や予防方法について紹介します。

5.1.胃薬を使用する
胃薬は、胃の粘膜を保護する薬、胃酸の分泌を抑える薬、胃の動きを良くする薬、逆に胃の動きを抑える薬など多くの種類があるため、薬局やドラッグストアで薬剤師に相談して、自分の症状に合った適切な薬を選んでもらうことをおすすめします。
5.2.ストレスを解消する
ストレス解消は、胃痛を改善、予防することにつながります。十分な睡眠時間で休息することが大切ですが、気分転換や軽い運動など、自分なりのストレス解消法を見つけるようにしましょう。
5.3.食習慣を改善する
胃に滞留時間が長く、負担が大きい脂肪分の多い食事や、刺激物やアルコールなど胃粘膜に直接影響を与える食べ物などは、なるべく控えるようにしましょう。暴飲暴食は避け、消化の良い物を腹八分目にすることが、胃痛の改善・予防に役立ちます。
5.4.睡眠をしっかり取る
前述の通り、胃酸や胃粘膜の分泌には、自律神経が関わっています。睡眠不足や睡眠の質の低下は、自律神経のバランスを乱す原因になるため、睡眠をしっかりとることが胃痛の改善・予防につながります。
5.5.禁煙する
たばこに含まれるニコチンは、胃や十二指腸の血管を収縮させ粘液の分泌を減らすだけでなく、胃液の分泌を増やす作用があり、胃の粘膜に対する攻撃因子が優位になることで、胃痛の原因になります。禁煙は、胃痛の改善・予防だけでなく、胃がんをはじめとしたさまざまな病気のリスクを減らすことがわかっているため、禁煙することが大切です。
5.6.医療機関を受診する
胃痛を改善する方法を試してもよくならない場合には、医療機関を受診することをおすすめします。その場合には、消化器内科の専門医のいるクリニックで、必要に応じて胃カメラができることが望ましいでしょう。胃カメラで胃の粘膜を直接観察することで、胃痛の原因を見つけて、適切な治療をすることができるからです。
胃痛の原因を調べる検査について説明します。
6.1.超音波検査(腹部エコー検査)
胃痛であっても、胃以外の臓器に病気があることも多いため、肝臓、胆のう、胆管、膵臓、脾臓、腎臓、子宮、卵巣、膀胱、前立腺、胃、小腸、大腸などを観察することができる腹部超音波検査は有用な検査です。腹部超音波検査は、おなかに超音波をあてて、臓器への反射波を映像としてとらえ、異常の有無を調べる検査です。
6.2.血液検査
胃痛の原因や胃痛を生じる病気の状態を調べるために、血液検査をおこないます。血液検査では、主に肝機能(AST、ALT、γGTPなど)、貧血(ヘモグロビンの数値)、炎症の有無(白血球数、CRP)などを調べます。
6.3.胃カメラ(胃内視鏡検査)
胃カメラは、口や鼻から胃カメラ用のスコープを挿入し、食道、胃、十二指腸の粘膜を直接観察する目的でおこなわれる検査です。胃痛がある場合に胃カメラをおこなうと、咽頭がん、喉頭がん、食道がん、逆流性食道炎、胃ポリープ、急性胃炎、慢性胃炎、胃潰瘍・十二指腸潰瘍、胃がん、胃アニサキス症などの病気の有無や、重症度などを診断することができ、適切な治療につなげることができます。また、必要があれば、胃カメラと同時に出血部の止血などの治療や、組織の一部を採取して病理診断をおこない、良性・悪性の確認もできます。
西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUでは、最新の内視鏡システムを導入し、可能な限り苦痛の少ない検査を目指しています。検査・治療は、総合病院で経験を積んだ日本消化器内視鏡専門医・指導医の資格を持った医師がおこない、AIによる見落とし防止システムも導入しています。受診当日や土曜日に検査することもできるため、胃痛の症状がある方は、是非ご相談ください。
胃痛は、ストレスや睡眠不足などによる自律神経のバランスの乱れや、暴飲暴食、刺激の強い食べ物、喫煙などによって引き起こされます。これらの要因により、胃酸分泌と粘液分泌のバランスが崩れ、胃の粘膜が傷つきやすくなることが原因です。
胃痛の原因となる病気には、胃の病気だけでなく、周辺の臓器の病気もあります。正確な診断のために、腹部超音波エコーや血液検査、胃カメラなどの検査がおこなわれます。特に胃カメラは、食道から胃、十二指腸までの粘膜を直接観察でき、確実な診断と治療につなげることができる有用な検査です。最近では、細いスコープや鎮静剤の使用、鼻からの挿入などにより、苦痛の少ない検査が可能になっています。胃痛がある場合は、一度胃カメラを受けることをおすすめします。

胃カメラ検査(胃の内視鏡検査)は、胃がんや食道がんの早期発見だけではなく、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍など、上部消化管のさまざまな病気の発見や診断・処置に役立つため、消化器内科領域で特に重要な検査の一つです。
ここでは、消化器内科医が推奨する胃カメラ検査の受診年齢や、検査を受けたほうが良い症状や見つかる病気などについて詳しく解説します。胃カメラ検査で見つけることのできる主な病気や、当院の「苦痛の少ない胃カメラ検査」についてもご紹介します。

胃カメラ検査は何歳から受けるべきでしょうか?胃カメラ検査の受診推奨年齢や、胃カメラ検査を受けたほうが良い症状等についてみていきましょう。
特に消化器に不調を感じていなくても、40歳以上の方には胃カメラ検査の受診を推奨します。なぜなら、40歳代から胃がんや食がんに罹患する人が増え始め、50歳以上になると胃がんや食がんの罹患率が本格的に増えるからです。胃がんや食道がんは、初期の段階では症状を自覚しづらく、発見が遅れがちです。40歳を過ぎたら、2〜3年に1回のペースで胃カメラ検査を受けることで、病気の早期発見・早期治療につなげることができます
ただし、次のような症状がある方は、年齢に関わらず胃カメラ検査を受けることをおすすめします。
1.2. 胃カメラ検査の受診を推奨する症状
以下のような症状がある方は、胃や食堂などに何らかの病気が潜んでいる可能性がありますので、年齢に関係なく、胃カメラ検査を受けることをおすすめします。
■ 胃痛、胸痛
■ 便の色がおかしい(黒っぽい)
■ 胸やけ・吐き気
■ 食べ物が飲み込みにくい
■ 体重減少・腹部膨満
その他、以下の生活習慣や背景のある方も、胃がんなどの罹患リスクが高いため、定期的に胃カメラ検査を受けることを推奨します。
■ 検診で食道・胃・十二指腸などの異常を指摘された
■ 飲酒習慣がある
■ 喫煙習慣がある
■ 肥満
■ 胃がんの家族歴がある(身内に胃がんにかかった人がいる)
胃内にヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)への感染が見つかった方は、1~2年に1回のペースでの定期的に胃カメラ検査を受けることをおすすめします。ピロリ菌に感染していると、胃粘膜に慢性的な炎症が起き、慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの病気を引き起こすリスクが高くなります。また、ピロリ菌に感染している方では、感染していない方に比べて、胃がんの罹患リスクが5倍になると報告されています。定期的に胃カメラ検査を受けることで、病気の早期発見、早期治療につなげることができます。

胃カメラ検査は、上部消化管に起こりうるさまざまな病気の早期発見に有効な検査です。胃カメラ検査で見つかる主な病気などについてみてみましょう。
胃粘膜の状態を観察することでピロリ菌の感染の有無を調べることができます。ピロリ菌感染を放置していると、胃潰瘍や十二指腸潰瘍に罹患する場合があります。また、萎縮性胃炎が進行し、その一部が胃がんに進展すると考えられています。したがって、ピロリ菌が見つかった場合には、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の発症リスクや生涯の胃がんのリスクを下げるため、内服薬を処方し、除菌治療をおこないます。
除菌方法は、
・胃酸を抑える薬1種類 (ボノプラザン)
・抗菌薬2種類(クラリスロマイシン+アモキシシリンか、メトロニダゾール+アモキシシリン)
の合計3種類の組み合わせを、1日2回朝夕、7日間服用します。
当院では便利なパック製剤を使用しています。
ピロリ菌を除菌した後も、胃がんリスクがゼロになるわけではありませんので、胃カメラ検査を受けることをおすすめします。
胃がんは、症状を自覚しづらいため、発見が遅れがちですが、胃粘膜表面を直接観察できる胃カメラ検査であれば、早期に発見することができます。がんが疑われる部位を見つけた場合は、組織を採取し、がん細胞の有無を調べるために生検に出し、がん細胞がみつかれば確定診断ができます。胃がんというと怖い病気のイメージがありますが、最も初期のステージⅠで早期発見し、適切な治療をおこなうことができれば、5年生存率は90%以上であり、根治が目指せます。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍は、胃または十二指腸の粘膜が強度に荒れて、ただれている状態です。胃潰瘍・十二指腸潰瘍になると、たいていみぞおちの痛みや吐き気、嘔吐、腹部膨満感などの自覚症状があり、ひどいと潰瘍から出血し、吐血やタール便(ドロドロした黒っぽい便)が出ます。しかし中には、潰瘍があっても自覚症状がなく、胃カメラによる胃がん検診で偶然発見されることも少なくありません。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍の患者さまの約80~90%はピロリ菌に感染していることや、ピロリ菌除菌治療によって、1年間の再発率が胃潰瘍で65%→11%、十二指腸潰瘍で85%→6%へ著明に低下することがわかっています。そのため、胃カメラ検査で胃潰瘍や十二指腸潰瘍が見つかった場合は、除菌治療をおすすめします。
バリウム検査と胃カメラ検査は、いずれも上部消化管内に異常がないかを調べる検査です。
胃カメラ検査は、スコープを胃の中まで挿入し、先端に内蔵したCCDカメラで、粘膜の形態変化(凹凸)や色調変化を直接観察する検査です。カメラを飲みこむことに不安を感じる方がおられますが、初期の小さな病変やわずかな色調変化を発見しやすく、疑わしい部位が見つかったときは同時に生検をおこない、確定診断することができます。
一方、バリウム検査は、バリウムという造影剤と発泡剤(胃を膨らませる薬)を飲み、レントゲン(X線)で撮影して消化管の様子を見る検査です。炎症や潰瘍、腫瘍による粘膜表面の凹凸や狭窄(せまくなっているところ)などを白黒の印影で映し出します。バリウム検査は、自治体や会社の検診などに付いていることもあるので、受けやすい検査ではありますが、カラーでの観察ができないことや、ごく初期の小さな異常を見つけにくいなどのデメリットがあります。また、万が一異常が見つかった場合には、胃カメラでの精密検査が必要になります。二度手間にならないためにも、初めから胃カメラ検査を受けることをおすすめします。

かつて胃カメラ検査は「痛い・苦しい」というイメージがありました。しかし、検査機器や検査技術の発達によって、現在では痛みや苦痛の少ない検査方法を選択できるようになっています。
胃カメラ検査にともなう痛みや苦しさが心配な方は、「経口内視鏡検査」に鎮静剤(眠り薬)を併用することで、うとうとと眠っている間に苦痛なく検査を受けることができます。もちろん個人差はあるものの、カメラ挿入時の嘔吐反射や、喉の痛み・圧迫感を感じることはほとんどありません。
ただし、鎮静剤を使用したくないという場合は、カメラを鼻から挿入する「経鼻内視鏡検査」を選択し、苦痛を軽減する方法もあります。鼻から挿入する経鼻内視鏡検査のほうが、覚醒下でも嘔吐反射を起こしにくく、管も細いため、喉を通過するときの圧迫感や痛みも少なくて済むことがほとんどです。ただ鼻腔内が狭い人の場合、カメラが鼻の中を通るときに痛みが生じることや、カメラの挿入ができないことがあるため、最適な検査方法については医師と相談しましょう。
当院の胃カメラ検査は、最新鋭の内視鏡システムとAIによる見落とし防止システムなどの最新技術を導入し、専門医・指導医の資格を持った医師による正確な検査・診断を実施するとともに、鎮静剤を併用しながら、患者さまにとって苦痛の少ない胃カメラを提供しています。
当院の内視鏡システムは富士フィルム社製のELUXEO 8000システム(2024年6月発売)を導入しています。メインの内視鏡は先端部径5.8mmという極めて細い高画質細径カメラを採用しており、操作性にも優れています。さらに、富士フィルム社製の「AIによる見落とし防止システム:CAD EYE」を組み合わせることで、正確な診断結果を導きます。検査中に疑わしい部位を発見し、組織採取や処置が必要になった場合も、先端部径9.8mmという極めて細い処置用内視鏡を使用し、安全かつ迅速に対応します。
日本消化器内視鏡専門医・指導医の資格を持ち、総合病院での経験が豊富な医師が検査・治療をおこないます。
日本消化器内視鏡専門医とは、医師の中でも消化器内視鏡診療に関する豊富な学識と経験を有する医師に与えられる資格で、取得するためには日本消化器内視鏡学会に5年以上所属し、消化器内視鏡学会が定めた研修や実技経験を積み、試験をクリアすることが求められます。
日本消化器内視鏡指導医は、専門医の資格を取得後、さらに3年経過し、高い診療能力と若手医師に対しての専門医取得のための指導がおこなえる能力を有する医師に与えられる資格です。
国内で胃カメラ検査を実施している医師の全てがこの専門医・指導医資格を持っているわけではないため、専門医・指導医による検査が受けられるのは、当院の大きな強みの一つです。
当院では、鎮静剤を投与し眠った状態で楽に胃カメラ検査が受けられます。鎮静剤を使用した方は、検査後、リカバリー室でゆっくりお休みいただき、はっきりと意識が回復してから帰宅していただけます。
胃カメラ検査は、胃などの上部消化管の病気の早期発見に欠かせない重要な検査です。上部消化器の病気は自覚症状がないことも多いため、不快な症状がない方でも、40歳を過ぎたら胃カメラ検査を定期的に受けることをおすすめします。胃カメラ検査を受ける間隔は、症状の有無やピロリ菌感染の有無によって個人差があるので、医師とよく相談しましょう。
胃カメラ検査といえば、苦しい・痛いというイメージを抱きがちですが、当院では、苦痛の少ない胃カメラ検査を提供しています。最新鋭の検査機器、経験豊富な医師による手技、検査方法の工夫によって、楽に検査を受けていただけますので、胃カメラ検査に不安のある方や、過去の検査で苦しい思いをした方も、気軽にご相談下さい。
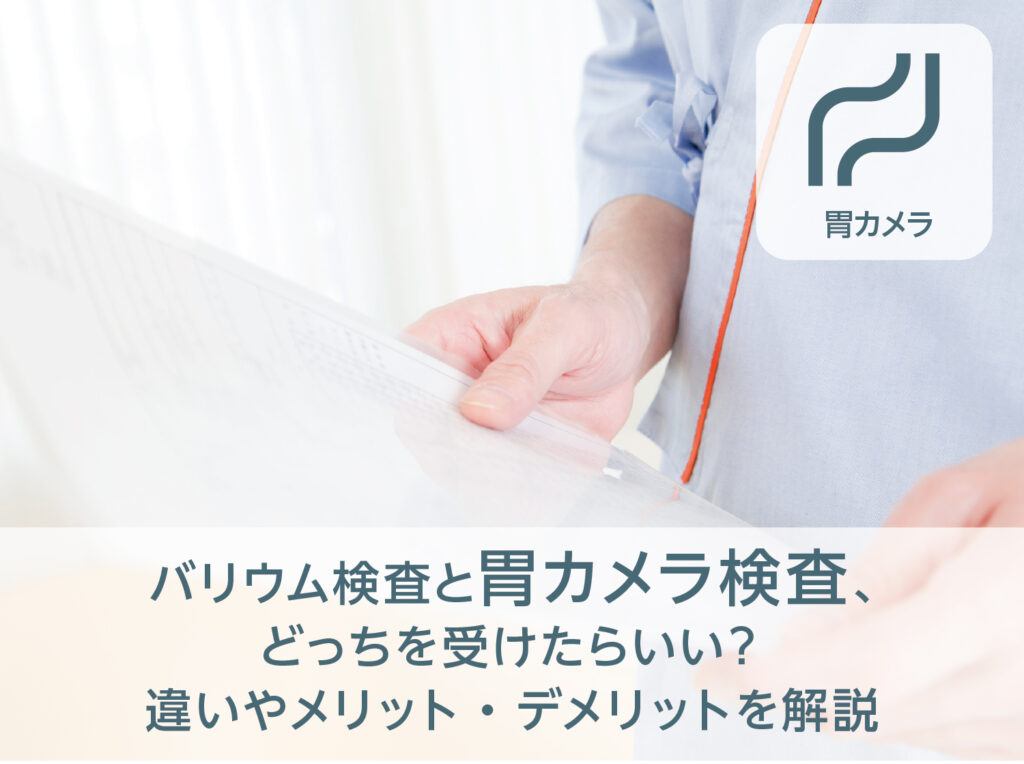
バリウム検査と胃カメラ検査は、どちらも上部消化管の情報を読み取ることのできる重要な検査です。胃がんや胃潰瘍、ポリープなどの病気の発見に役立つもので、企業の定期健康診断や自治体のがん検診として受けられる機会も増えています。
本記事では、「バリウム検査と胃カメラ検査のどちらを受ければいい?」という悩みを持つ方のために、バリウム検査と胃カメラ検査の違いや検査の方法、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説します。
バリウム検査と胃カメラ検査は、いずれも上部消化管内に異常がないかを調べる検査です。食道から十二指腸までの上部消化管を観察することができ、胃がんなどの病気を早期に発見するために重要です。現在、胃がんを直接診断するための検査として、科学的根拠に基づいて国が推奨しているのは、バリウム検査と胃カメラ検査の2つです。
バリウム検査と胃カメラの違いについて詳しくみていきましょう。
バリウム検査は、バリウムという造影剤と発泡剤(胃を膨らませる薬)を飲み、レントゲン(X線)で撮影して消化管の様子を見る検査です。胃や食道の粘膜は、そのままではレントゲンに映らないため、造影剤を飲んだ状態で身体の向きを変えることで、食道や胃の壁に造影剤を広げ、上部消化管の粘膜表面の凹凸(炎症や潰瘍、腫瘍など)や狭窄(せまくなっているところ)などを映し出します。正常な胃であれば、粘膜のヒダが整っていますが、粘膜上に異常があると、凹凸部分にバリウムが溜まってその影が観察できます。
バリウム検査は、正式には「上部消化管X線検査」または「上部消化管造影検査」といいます。一般的には「胃X線検査」や「胃レントゲン検査」と呼ぶこともあります。
バリウム検査のがん診断精度は約70〜80%といわれており、胃がんを早期発見することにより胃がん死亡率を40~50%減少させる効果が認められています。
胃がんのほかに、胃潰瘍(いかいよう)、胃ポリープ、胃憩室(いけいしつ)、胃粘膜下腫瘍、その他胃隆起性病変や食道がん、食道潰瘍、食道ポリープ、食道アカラシア、十二指腸潰瘍、十二指腸憩室などの病気の発見につながります。
胃カメラ検査は、スコープを胃の中まで挿入し、先端に内蔵したCCDカメラで、粘膜の形態変化(凹凸)や色調変化を直接観察する検査です。正式名称を「上部消化管内視鏡検査」といいます。
胃カメラを口から入れる場合には、オエっとなる嘔吐反射を抑えるため、あらかじめ喉に麻酔をしたり、あるいは鼻からカメラを挿入する方法、鎮静剤を併用して眠った状態で検査をおこなうなど、楽に検査が受けられるように工夫することもあります。
胃カメラ検査では、粘膜上にまだ凹凸のないごく初期のがんであっても、わずかな色調変化から異常を検出することができるため、がんなどの病気の早期発見に高い効果を発揮します。
胃カメラ検査による早期発見によって、胃がんによる死亡リスクを61%減少させる効果が認められています。
胃がんのほかに、胃炎、胃潰瘍、胃ポリープ、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染の有無、胃アニサキス、逆流性食道炎、食道がん、バレット食道、十二指腸がんなどの病気の発見につながります。

胃がん検診として、胃カメラ検査と共に推奨されているバリウム検査ですが、メリットとデメリットが存在します。バリウム検査のメリット・デメリットについて詳しくみていきましょう。
バリウム検査の主なメリットは、
の3つです。
バリウム検査は、費用が保険適用外で1万円前後と胃カメラ検査に比べて安く、自治体によっては無料で受けることもできます。
また、バリウム検査は、病変の形態・大きさ・位置や硬さを客観的に把握することも可能なため、内視鏡検査の短所をカバーすることができます。
検査時間も10分程度と短時間であり、比較的簡単に受けられるので、会社の定期健康診断に付加されていることも多く、受診機会が得られやすいのもメリットです。
バリウム検査のデメリットは、
などがあります。
バリウム検査では、白黒のX線写真で判定をするため、胃粘膜の色調が確認できないことや、凹凸の少ないタイプのがんは判別しにくいことがあります。また、胃液が多い人の場合、胃液が胃粘膜へのバリウムの付着を邪魔することで、検査精度が低下することがあります。そのほか、バリウム自体が飲みにくいことに加え、発泡剤の効果を持続させるため、込み上げるゲップを堪える必要があります。バリウム検査は比較的簡単で短時間で終わるものですが、途中でゲップをしてしまうと、再度発泡剤を飲まなくてはなりません。また、バリウムを誤嚥してしまうリスクがあることや、検査後に下剤を服用してバリウムを体外に排出しきらなくてはならないため、頻回にトイレに行くことで行動が制限されることがあります。バリウムを完全に排出しないと、便が腸に詰まる「腸閉塞」という重篤な状態に陥るリスクもあります。
バリウム検査では、人体に影響のない範囲ではあるものの、放射線被爆をともなうこともデメリットの一つです。また、バリウム検査の結果、精密検査が必要と判断された場合には、追加で胃カメラ検査が必要になります。
胃カメラ検査にもメリットとデメリットがあります。
胃カメラ検査のメリットとデメリットを詳しくみていきましょう。
胃カメラ検査のメリットは、
などです。
胃カメラ検査では、バリウム検査のように放射線被爆の心配がありません。消化管内部に挿入したカメラで直接粘膜の詳細な観察ができ、視野もカラーのため、初期の食道がんや小さな病変の発見や粘膜上の凹凸や形状、色も確認することができます。また、観察中に疑わしい病変を発見したときは、その場で組織を採取し生検に出すことができるなど、得られる情報が多いのが大きなメリットです。
胃カメラを挿入するときの不快感や不安感も、鎮静剤や喉の麻酔を適宜併用することで、苦痛を軽減し、楽に検査を受けることができるのも胃カメラの利点です。
胃カメラ検査のデメリットは、
などです。
胃カメラ検査では、きわめて稀ではありますが、胃カメラが粘膜を傷つけ、出血や穿孔などの合併症を起こすリスクや麻酔薬に対するアレルギー症状を起こすリスクが存在します。
また、胃カメラを飲みこむ際に嘔吐反射が起こりやすい方がおられますので、その場合は苦痛の軽減を目的に鎮静剤を併用します。鎮静剤の成分によって眠気や目がかすむなどの影響が出ることがあるため、当日は運転や精密な作業ができないので注意しましょう。
費用面でも、胃カメラ検査はバリウム検査と比較するとやや高額である傾向があります。
バリウム検査も胃カメラ検査についても、検査が受けられない場合があります。検査を検討する際は、以下に該当しないか確認しましょう。
バリウム検査は、妊娠中または妊娠の可能性のある方や、バリウムや発泡剤へのアレルギーがある方、自分で体位が変換できない方、嚥下(飲み込む)機能に障害のある方、検査前72時間に排便がなく便秘の状態の方は受けることができません。また、体重が概ね130㎏以上の方も、検査機器の耐荷重を超えるため、受けることができません。そのほか、糖尿病の方や循環器、呼吸器、消化器に大きな病気のある方は、検査を受ける前に医師の判断が必要になる場合があります。
胃カメラ検査を受けられないケースは少ないものの、喉の病気のためにカメラを挿入できない方や、重度の呼吸不全でカメラの挿入で酸素濃度が極端に下がり得る方など全身状態が極端に不良の方は適応がありません。
バリウム検査と胃カメラ検査を選べるのであれば、胃カメラ検査を受けることをおすすめします。バリウム検査は比較的受けやすく、消化器全体のバランスを把握することにおいてはメリットがありますが、白黒のレントゲン画像で判断するため、粘膜上のわずかな凹凸や色調変化を捉えることができません。その点胃カメラ検査であれば、消化管粘膜を直接カラーで詳細に観察することができ、万が一、疑わしい部位が見つかった場合でも、その場で組織を採取することができるなど、一回の検査で得られる情報が多く、ごく初期の胃がんや食道がんの発見にもつながります。
「胃カメラは苦しそう」「痛そう」というイメージから、胃カメラ検査を受けることに対して強い不安がある場合も、嘔吐反射が出にくい経鼻内視鏡(鼻から入れる胃カメラ)や、鎮静剤の併用を選択頂けますので、自分に合った方法を選ぶことで楽に胃カメラ検査を受けることができます。
バリウム検査と胃カメラ検査は、共に胃がん検診として国が推奨している検査です。検査を受けるにあたっては、それぞれにメリットとデメリットが存在することや、検査方法の違いを知った上で選択するようにしましょう。どちらの検査でも、妊娠中の方や大きな病気にかかったことのある方など、検査が受けられない場合がありますので、心当たりのある方は事前に医師に相談するようにしましょう。