大腸がんは年々増加しており、新規の患者数は男女ともにすべてのがんのなかで2番目に多く、亡くなる方の数も男性が2位、女性では1位と非常に多くなっています。背景には、ゆっくり進行するため症状が現れにくく、早期発見が難しいという大腸がんの特徴があります。増え続ける大腸がんで命を落とさないために、大腸がんの症状について詳しく解説するとともに、国が推奨する大腸がん検診の概要やメリット・デメリットについてもお伝えします。大腸がんに対する正しい知識を踏まえて、大腸がんの早期発見・早期治療について解説します。
ヒトの消化管は食道、胃、小腸と続き、大腸へとつながります。大腸は右の下腹部から上へと延び、胃の下側を通って左に進み、下に降りて肛門へとつながっています。大腸は結腸と直腸とに区分され、小腸との境目からおなかの中をぐるりと回って下腹部の中心までが結腸、そこから肛門までまっすぐに延びているのが直腸です。大腸の壁は、内側から「粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層(しょうまくかそう)、漿膜」と呼ばれる5層から成り立っています。
大腸の内側は粘膜に覆われており、その外側を筋肉が取り囲んでいます。胃と小腸で消化された食べ物の残りカスから水分を吸収し、便を形づくりながら肛門まで運ぶのが、大腸の主な役割です。
大腸は結腸と直腸に分けられますが、結腸と直腸もさらに細かく区分されています。結腸は、大腸のスタート地点となる盲腸、そこから上へと延びる上行結腸、上腹部を左に向かう横行結腸、左下腹部へと下がる下行結腸、からだの中心部へと向かい直腸につながるS状結腸に区分されます。
直腸は、S状結腸と接続する直腸S状部、直腸S状部から腹膜の下端あたりまでが上部直腸、そこから肛門に至るまでが下部直腸に区分されます。
初期の大腸がんは無症状で、がんが進行することにより、便に血が混じる、便の表面に血が付着するなどの症状があらわれます。ほかにも便秘や下痢、便が細くなるなどのほか、慢性的な出血による貧血、体重の減少などがみられる場合もあります。さらにがんが進行すると腸閉塞を起こすこともあります。
通常、大腸がん自体による痛みはありませんが、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)による痛みや、肛門痛として感じる痛みもあります。しかし、いずれの症状も大腸がんに特有の症状ではなく、ほかの病気で起こる可能性もあります。症状だけでは診断ができないため、定期的に大腸がんの検査をおこなうことが推奨されます。

初期の大腸がんの診断には、便に血液が混じっていないかを調べる便潜血や、医師が手指によって直腸内を触診する直腸指診などがあります。便潜血検査などで大腸がんが疑われる場合には、肛門から造影剤を注入しておこなう注腸検査や大腸内視鏡検査などの画像診断による精密検査がおこなわれます。
便潜血検査とは、排出された便のなかに混じりこんだ血液の反応を調べる検査です。便潜血検査で陽性になっても、必ずしもがんによる出血とは限りませんが、出血の原因を調べるために精密検査が必要となるので、大腸がんの一次検査としておこなわれます。大腸がんには自覚症状がないため、がん患者が増え始める40歳を過ぎたら、年に1回は便潜血検査を受けましょう。
便潜血検査で陽性になると、精密検査の対象となります。精密検査では主に大腸内視鏡やX線造影を使用して大腸内の観察をおこないます。一般的には、肛門から内視鏡を挿入し、直腸、結腸、盲腸まで大腸内をすべて観察する「全大腸内視鏡検査」が第一選択肢となります。
西宮敬愛会病院 低侵襲治療部門 COKU」の内視鏡検査ではがんやがんの疑いがあるポリープなどを発見するだけではなく、その場で切除可能なポリープであれば、癌の疑いのものも切除が可能です(一部例外はあります)。残念ながら外科手術が必要と判断された場合も、病変部の細胞を採取して病理検査をおこなうことができます。
内視鏡で切除したポリープが癌であった場合、癌の性質を顕微鏡で詳しく分析し、転移のリスクがあるかの評価を行います。その結果、追加で外科手術を行うべきと判断される病変、あるいは初めから外科手術が適当であると判断された病変については、CTやMRI、腹部超音波などさまざまな医用画像診断機器を用いて、腫瘍の大きさや位置の正確な把握、リンパ節や他の臓器への転移がないかを調べられます。また、経過を観察するために採血による腫瘍マーカー検査がおこなわれます。
初期の大腸がんにはほとんど症状がないため、自覚することは困難です。がん検診の推奨年齢になったら検診を受けることに加え、少しの体調の変化でも自己判断で放っておかず、できるだけ早く医療機関を受診することが早期発見のポイントです。
自覚症状のない初期の大腸がんを早い段階で発見するには、定期的に大腸がん検診を受けることが大切です。大腸がん検診は医師による問診と、2日間分の便を採取して血液反応の有無を調べる便潜血検査です。
企業には、事業所の規模に関係なく従業員に年1回の健康診断が義務付けられており、40歳以上は便潜血検査が検査項目に含まれています。個人事業主など企業に勤めていない40歳以上の方には、1年に1回、市町村から大腸がん検診のお知らせが届きます。自治体による大腸がん検診は健康増進法に基づいて実施されており、数百円~千円程度の自己負担で受けることができます。
大腸がん検診は、医師による問診と便を採取するだけの簡単な検査ですが、自覚症状のない大腸がんの早期発見にはとても重要です。40歳を過ぎたら年に1回の大腸がん検診を必ず受けましょう。
大腸がん検診のメリットは、自覚症状のない初期の大腸がんを発見できることにあります。便の採取だけで診断可能であり、被験者には大きな利益となります。一方で、診断結果によっては以下のような不利益をこうむる場合もあります。
■偽陰性
偽陰性とは、がんがあるにも関わらず、病変や兆候が発見できず精密検査不要と判定されてしまうことです。このリスクを回避するためには、1度きりの検査ではなく定期的にがん検診を受けることが大切です。
■偽陽性
逆に、がんがないにも関わらず、要精密検査と判定されてしまうのが偽陰性です。精密検査には費用がかかりますし、検査による身体的な負担、診断結果を待つあいだの不安な気持ちなど、被験者にとってさまざまな不利益があります。
ただ、「がんの疑い」を発見するのががん検診の目的であることから、残念ですが偽陽性をなくすことは困難です。この点を理解した上で検診にのぞむ心構えが必要です。
そのほか、大腸内視鏡検査にともなう下剤や造影剤の使用によって起こるアレルギーや腸閉塞、非常に確率は低いものの内視鏡によって大腸内を傷つけてしまうなど、偶発的なリスクがあります。
ただし、大腸がん検診は受ける回数が多いほど、大腸がんによる死亡率が低くなることが分かっています。また、大腸内視鏡検査は、大腸がんだけでなく、他の病気の発見にも有益です。受診することによる利益と不利益をよく理解した上で、大腸がん検診を受診してください。
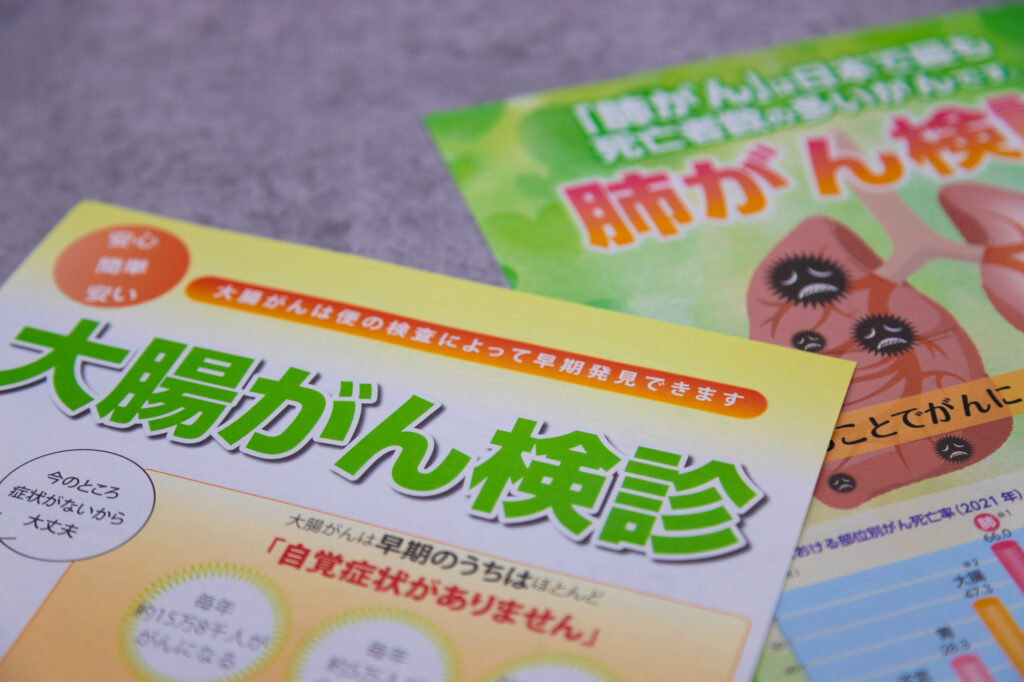
大腸がんの多くは大腸の内壁にできる潰瘍状の腫瘍で、比較的進行は遅いと考えられています。そのため、大腸がん検診で早期発見できれば、がんが進行する前に治療することが可能で、身体的負担の少ない治療で済むと同時に、がんによる死亡率を下げる効果が期待できます。
また、大腸内視鏡検査ではがん化する可能性のある腫瘍やポリープなどを検査と同時に切除することが可能で、病変部のがん化を防ぐというメリットがあります。
大腸がん検診では、がんではない良性の腫瘍や、進行が遅く本来なら経過観察で済むようながんでも、治療の対象としてしまうことがあります。検査によって見つかったがんの危険度を正確に見極めることは難しく、本来必要のない治療によって経済的な負担や心身の負担がメリットとなります。
大腸がんにかかる割合は、男女とも40歳を過ぎるころから増え始めるため、大腸がん検診は40歳以上を対象としています。40歳未満の大腸がんリスクは低く、若い方の受診は偽陽性と判定されるデメリットがメリットを上回ると考えられます。
2020年の調査によると、人口10万人当たりの大腸がんにかかる割合は、30代前半では男性6.3人、女性5.8人ですが、40代前半になると男性24.4人、女性21.8人と急増し、40代後半では男性42.2人、女性35.2人まで増えています。
大腸がんは40歳からが適齢期と考えられるため、年に1度の大腸がん検診がいかに重要かわかります。また、大腸がん検診を受けているからと安心せず、気になる症状のある方は消化器内科を受診しましょう。以下のような症状・特徴にあてはまる方は大腸内視鏡(大腸カメラ)による検査をおすすめします。
■血便・下痢や便秘など便通異常
■おなかがはる・腹痛
■検便(便潜血検査)にひっかかった
■血縁に大腸癌の方がいる
■喫煙習慣がある
■飲酒習慣がある
大腸がんには固有の初期症状がなく、なんらかの症状に気づいた時には進行がんになっている可能性があります。血便はもちろんですが、下痢や便秘などの便通異常、腹痛やおなかの張り、しこりや肛門痛などの症状を軽く見ず、早めに消化器内科を受診することが大切です。大腸内視鏡検査により、大腸がんだけでなくほかの病気が見つかる可能性もあります。
また、大腸がんは40歳以上になると急増するため、勤務先の健康診断や自治体による大腸がん検診を活用しましょう。大腸がんの早期発見には定期的に大腸がん検診を受けることが最も重要なポイントです。40歳を過ぎたら、年に一度の大腸がん検診を忘れずに受けましょう。